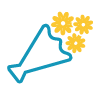令和7年3月25日 市長記者会見

出席者
市長、総務部長、企画調整部長、文化スポーツ部長、商工観光部長
内容
発表事項
1.令和7年度 人事異動内示について
2.山形市発展計画2030の策定について
3.山形市役所前待合所オープニングセレモニーの開催について
4.山形市コミュニティサイクルの愛称について
5.山形市地域活性化プレミアム付電子商品券(ベニpay)募集【第6弾】について
6.第32回 霞城観桜会について
7.第25回 馬見ヶ崎さくらラインライトアップ
8.山形市指定文化財の指定について
資料のみ
1.山形市産材「ベニうっど」ロゴデザインのお披露目について
2.令和7年繁忙期に係る平日窓口延長及び休日窓口の開設について
会見内容
映像
発表内容(※要点筆記としておりますので、あらかじめご了承ください。)
市長
先ほど、令和7年度の人事異動について内示を行いましたので、発表いたします。
「山形市発展計画2030」の初年度となるため、健康医療先進都市及び文化創造都市の実現に向けて、目指すまちの姿に向けた取組を推進するとともに、市民目線の行政とチャレンジする市政を基本姿勢とし、地域の課題解決や経済活動・人流の活性化に向けた取組みを推進することを念頭に職員体制を整備しました。
人事異動の概要ですが、異動者の総数は1,327名であり、異動人数は昨年より275名の増となりました。
今年度末で、勤務延長していた、まちづくり政策部長が定年退職を迎えるほか、財政部長、財政部公共施設管理推進監、山形広域環境事務組合事務局長、福祉推進部長、上下水道部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び済生館看護部長などの部長級職員の10名が役職定年を迎えることから、次期発展計画に掲げる施策の推進を図るため、その後任人事を中心に人事異動作業を進めてきました。
それらを踏まえ、まず、管理職の昇任の内訳ですが、部長級への昇任者は11名、次長級昇任者は13名、課長級昇任者は40名であります。
また、若手・中堅職員について、人事評価の結果を踏まえ、
主幹級及び主査級への昇任を通常より早期に実施しております。主幹級への昇任者は30名で昨年より15名増加し、主査級への昇任者は67名で昨年より22名の増加となりました。早期昇任を通じて、将来の幹部職員候補を育成し、組織の更なる強化と活性化を図ってまいります。
女性職員については、将来の幹部職員登用も展望しながら積極的な昇任配置を心がけており、女性の管理職の人数は昨年の47名から3名増え、過去最高の50名となっております。
また、全管理職に占める女性職員の割合についても、昨年の21.7%から0.5ポイント増え、こちらも過去最高の22.2%となっております。
なお、管理職ではありませんが、次の管理職候補となる課長補佐級、係長級についても積極的な女性の登用を図りました。
今回の異動の結果、女性の課長補佐級の人数は、63名となります。
また、女性の係長級の人数は106名となり、これは係長級全体の35.6%にあたることから、今後も、女性管理職の割合が上がってくるものと考えております。
次に、組織編成における主な変更点を申し上げます。
一つ目は、「山形市発展計画2030」を推進するために、各部における政策立案機能及び総合調整機能を強化する視点で、組織名称の変更を行っております。
二つ目は、ニーズに応じて、より迅速・的確に業務を遂行していくため、これまでの課内室を課相当の組織へ格上げをしております。
三つ目は、新市民会館整備及びスポーツ施設整備の業務分担を明確化し、迅速・的確に業務を遂行していくため、文化スポーツ施設整備室を廃止し、新市民会館整備室及びスポーツ施設整備室を新設します。
四つ目は、健康医療先進都市の確立に向け、より強力に政策を実施し、展開していくことを明確化するため、保健総務課を保健政策課へ名称を変更します。
五つ目は、基本構想策定を受け、整備の具体化に向けて日本一の観光案内所準備室を日本一の観光案内所整備室へ名称を変更します。
六つ目は、粋七エリア整備事業や街路事業の推進に向けた用地取得の円滑化、工事契約事務のさらなる適正化と効率化及び建設DXを推進するための体制強化を図るため、まちづくり政策部に建設契約課を新設します。
七つ目は、消防本部内の業務改善及び組織の活性化にさらに積極的に取り組み、職員のモチベーションアップを図るため、消防本部にK2プロジェクト推進室を新設します。
八つ目は、学校卒業生や企業の「学校を応援したい気持ち」を応援する仕組みを構築し、さまざまな教育環境の整備にも役立てるため、教育委員会に企業・卒業生連携室を新設します。
次に、国・県・他市町村との人事交流及び職員派遣について申し上げます。
国への職員派遣は、総務省及び国土交通省との人事交流と総務省消防庁への職員の派遣を継続し、国の政策と市の事業の連携を深めるとともに、組織活性化と人材育成を図ってまいります。
山形県への職員派遣については、山形県消防学校及び山形県消防防災航空隊への消防職員の派遣を継続します。
他市への職員派遣については、東日本大震災の復旧事業に従事するため、福島県楢葉町に土木職の職員の派遣を継続します。
また、地方税に関する事務の合理化及び納税義務者等の利便性向上のため、地方税共同機構への派遣を継続します。
人事異動全般としては、適材適所の原則のもと、組織の活性化並びに職員のキャリア形成・ジョブローテーションの観点から、部局間を含め積極的な異動を行いました。
また、職員の意欲向上を図るため、職員申告における職務などへの希望等を十分に考慮し、可能な限り人事異動に反映しました。
以上が人事異動の概要でありますが、常に市民目線で考える行政、また、より一層効率的な行政を進め、「山形市発展計画2030」に基づく事業の推進と公約に掲げた政策の実現に向け、さらに気を引き締めながら、全力を尽くしてまいります。
人事については以上でございます。
それでは、定例の案件に移らせていただきます。
はじめに、山形市発展計画2030の策定について発表いたします。
山形市の最上位計画である「山形市発展計画2025」が、今年度をもって計画期間満了を迎えることから、新たに「山形市発展計画2030」を策定しました。
これまで、「健康医療先進都市」「文化創造都市」の2大ビジョンのもと、市民目線の行政、チャレンジする市政を基本姿勢に、まちの魅力を高めるため、様々なチャレンジを行ってまいりました。
その結果、先般、公表されました地価公示では、全国の県庁所在地の自治体で、連続して地価が上昇している自治体は非常に少ない中、住宅地で10年、商業地で8年、工業地で9年連続して地価の上昇を達成しております。
また、毎年行っております歩行者通行量調査では、令和5年・令和6年と連続して、平成21年以来の最高値を更新するなど、中心市街地グランドデザインのテーマでもあります「歩くほど幸せになるまち」の具現化が進んでいることを実感しております。
新たな発展計画は、2大ビジョン及び基本姿勢を引き続き堅持した上で、持続可能なまちづくりという点を重視し、ゴールとなるべき目指すまちの姿を描き、現時点から取り組むことを考えるバックキャスティングの考え方を全面的に取り入れております。
バックキャスティングの起点は少子高齢化の進行に伴い様々な課題が顕在化するとされる2040年とし、目指すまちの姿を「健康医療先進都市・文化創造都市を確立し、選ばれるまちとなる」と定めました。
ここで、お配りしている「発展計画2030」本編をご覧ください。
表紙の裏面、目次にあるとおり、本編は第1章から第5章までの構成としております。
主な箇所について、説明させていただきます。
はじめに、34・35ページをご覧ください。
このページでは、2040年の目指すまちの姿について、記載しております。具体には、「山形市が持つ「健康医療資源」「文化芸術資源」をはじめとした地域資源の強みを活かし、市民・事業者・行政が一体となって「健康医療先進都市・文化創造都市」の確立に向けた取組を進めた結果、「健康医療先進都市・文化創造都市」の都市ブランドが確立し、山形らしさが輝いている。
また、人口減少対策をはじめ、顕在化してくる課題にもしっかりと対応している。
これらにより、市民や市外の方にとっても、山形市がさらに個性的で魅力的なまちとなっている。
そして「山形市に行きたい、働きたい、学びたい、住み続けたい」など、山形市を求める人々が増え、経済社会活動や観光等、人流がより活発になる「選ばれるまち」となっている。」
このような姿を描いております。
続いて、36・37ページをご覧ください。
このページでは、2040年の目指すまちの姿のイメージをイラストとして表現しております。このページと表紙のイラストについては、山形市地域おこし協力隊として従事している「髙安恭介さん」に描いていただきました。最終ページに、イラストのコンセプトを記載しておりますのでご覧いただければと思います。
続いて、40・41ページをご覧ください。
2040年の目指すまちの姿の実現に向けた、政策体系を示すページとなります。
発展計画2030は、目指すまちの姿の実現に向け、「1.まちをつくる」「2.ひとを育む」「3.しごとを豊かにする」の3つのテーマとこれらを支える行政経営に、公共交通をはじめとする19の政策分野を位置づけ、施策を推進してまいります。
施策の推進にあたっては、国の考え方や社会の基盤のベースとなる視点として「(1)こどもまんなか」「(2)強靭なまちづくり」「(3)SDGs」「(4)多様な価値観の尊重」を、新しい技術、市民生活や行政の事務を変革していくイノベーションの視点として「(5)DXの推進」「➅GXの推進」を、前例のない課題や未知の問題に対して最適な解決を図るためのデザインの視点として「(7)公共交通の活用」「(8)公民・広域・多機能連携」「(9)地域資源の発掘・活用・創造」を、それぞれ施策共通の横ぐしとし、幅広い連携を図りながら進めてまいります。
最後に、44ページから81ページまでは、公共交通から行政まで19の政策分野ごとに、具体の施策内容や成果指標などをまとめております。
44・45ページをご覧ください。
公共交通を例にいたしますと、2040年のまちの姿として、中心市街地や観光地をはじめ、教育機関や文化・スポーツ施設など主要な公共施設などが、多様な移動手段で高頻度かつシームレスに結ばれ、高齢者をはじめ、学生や来訪者など、誰もが多様な移動手段を選択し快適に移動することができるとともに、市内外からの人流が活発になり、暮らしやすく、健康で活気あるまちが形成さている姿を描いております。
その実現のため、鉄道や路線バスの高頻度化、各種実証運行等モデル事業の本格運行・他地区への横展開など地域特性に応じた公共交通の整備と、既存公共交通の維持改善や、市南部新駅と楯山駅周辺整備などの「交通軸」と「交通結節点」が有機的に接続した持続可能な公共交通ネットワークの構築、そして仙台市をはじめ連携中枢都市圏の連携市町など地域間を結ぶ広域公共交通の充実に取り組んでまいります。
このように、発展計画2030の取組により、他都市にはない、山形市が持つ固有の資源・強みをさらに伸ばすことで、2大ビジョンを都市ブランドとして確立させ、市民の方、市外の方にとっても山形市が個性溢れる魅力的なまちとなり、「山形市に行きたい、働きたい、学びたい、住み続けたい」など、山形市を求める人々が増え、社会経済活動や観光、人流がより活発になる「選ばれるまち」を目指し、市民、事業者とも連携し、一体となって取り組んでまいりたいと思います。
本編につきましては、山形市公式ホームページで公開しております。今後、5年間の山形市のまちづくりを示す計画となりますので、ぜひご覧いただきますようお願いいたします。
続きまして、山形市役所前待合所のオープニングセレモニーについて発表いたします。
山形市では、バス利用者の利便性向上とまちなかの滞在空間を創出するため、山形市役所前待合所のリノベーションを進めてまいりました。
このたび、供用を開始するにあたり、4月2日午前9時30分からオープニングセレモニーを行います。
今回の事業は設計施工一括発注方式で実施しており、事業者の工夫を凝らした提案のもと待合所のリノベーションを行いましたので、その概要をご説明いたします。
閉鎖されていた事務室の撤去を行い、待合スペースを拡張するとともに、壁面や天井については、木製のルーバーを設置し、温かみのある空間としております。
また、今年度愛称を決定した市産材「べにうっど」を活用した固定型のベンチとハイカウンターを設置しました。
更に、バスの接近情報を表示するデジタルサイネージを設置するとともに、自動ドアや冷暖房設備、防犯カメラを新たに設置しましたので、バスの到着まで快適にお待ちいただけます。
オープニングセレモニー当日は、山形市産材「べにうっど」のロゴデザインのお披露目も行います。製作者は東北芸術工科大学グラフィックデザイン科の高野真実さんです。当日は高野(たかの)さんからデザインのコンセプトについてご説明をいただくことになっております。
山形市役所前待合所は、バスの待合としてだけでなく、まちなかの滞在空間のひとつとしてもお使いいただけますので、ぜひ、多くの皆様にご利用いただきたいと思います。
続きまして、山形市コミュニティサイクルの愛称について発表いたします。
山形市コミュニティサイクルつきましては、事業を開始してから2年以上経過し、新たな移動手段として、市民の皆様をはじめ多くの方に広く浸透しております。このたび、愛着と親しみを深めていただき、更なる利用拡大を図るため、愛称を募集しました。
その結果、1,351件の応募があり、971作品の中から選考した結果、『ベニちゃり』と決定いたしました。
『ベニちゃり』は、応募いただいた中で69票と一番多かった作品です。また、山形市の花である「ベニバナ」や山形市のお宝広報大使「はながたベニちゃん」と自転車の意味をもつ「ちゃり」を組み合わせたものとなっており、誰でも覚えやすく、親しみやすい愛称となっております。
今後、『ベニちゃり』にふさわしい、ロゴマークを検討し、サイクルポートやパンフレット、ホームページなどで広報してまいります。
続きまして、山形市地域活性化プレミアム付電子商品券「ベニpay」の第6弾について発表いたします。
物価高による影響を緩和し、消費喚起を促すことで、地域経済の活性化を図るため、山形市地域活性化プレミアム付電子商品券「ベニpay」の第6弾を実施いたします。
今回の第6弾は、1口5,000円で、6,250円分の電子商品券を30万口販売いたします。
スマートフォンアプリ「ベニpay」にて、4月7日月曜日から、1人あたりの申込上限を4口とし、申込を受け付けます。申込多数の場合は抽選とし、利用期間は、令和7年9月30日火曜日までの予定です。
また、スマートフォンの扱いに不慣れな購入希望者向けに、よりきめ細やかな対応をとれるよう、コールセンターを設置するほか、第5弾でもご好評をいただきました出張窓口を、市内のコミュニティセンター4カ所に引き続き設置し、申込補助を実施してまいります。
ぜひこの機会に、お得な商品券をご活用いただき、地域経済の回復にご協力いただきたいと思います。
続きまして、春の桜イベントの開催について発表いたします。
今年も春の風物詩、「霞城観桜会」「馬見ヶ崎さくらラインライトアップ」が開催されます。
「霞城観桜会」につきましては、東大手門付近のお堀沿いの桜及び園内の桜のライトアップを行います。
また、4月12日と13日には、東堀に船を浮かべ、船上で演舞などを行う「風流花見流し」、東大手門広場付近での大茶会や筝曲演奏など雅な催しを開催する予定です。
次に、「馬見ヶ崎さくらラインライトアップ」につきましては、愛宕橋下流からあたご保育園まで約830メートルの区間をライトアップするほか、愛宕橋欄干の光装飾やちょうちん、ぼんぼり、そして模擬店を設置予定です。4月12日と13日には、キッチンカー・飲食ブースの設置など、来ていただいた方により楽しんでいただけるイベントの開催も予定しております。
ライトアップの期間は、両会場ともに桜の咲き始めから散りはじめまでとなります。市民の皆様にはぜひ会場に足を運んでいただき、山形の春を感じ、昼夜異なる桜を楽しんでいただきたいと思います。
続きまして、山形市指定文化財の指定について発表いたします。
2件の有形文化財について、市の歴史を知るうえで貴重な歴史資料であり、保存・活用することで、地域の歴史や文化への理解を促し、郷土への誇りや愛着を育むことにつながることから、2月19日に山形市の指定文化財に指定いたしました。
1件目の「木造釈迦如来坐像」は、若木に所在する廣福寺の本尊であります。木製の寄木造で、表現や構造などの特徴から、南北朝時代の作品であるとともに、京都の仏師の一派である「院派」の製作と推定されます。院派は、足利将軍家や各地の守護に関わる造像を行っており、本仏像の製作に斯波兼頼が関わったことが想定される貴重な歴史資料であることから、市の文化財に指定いたしました。
2件目の「銅造菩薩立像」は、山寺に所在する中性院の仏像です。銅製で鋳造されている菩薩形の立像で、表現や構造などの特徴から、奈良時代後半の製作と考えられます。全体として繊細な表現で作られている金銅仏で、本市にとって最古の仏像遺品となる貴重な歴史資料であることから、市の文化財に指定しました。
なお、今回の指定により、市指定文化財は全部で95件となりました。
私からの発表は、以上でございます。
(人事)
山形新聞社
女性の管理職で過去最高の22.2%ということで、市長の受け止めをお聞かせください。
佐藤市長
女性職員の皆さんには、今、管理職としても大変活躍をしていただいているところであります。やはり年齢層が上に行けば行くほど、職員の同世代間での女性割合が低い傾向にありますので、これからどんどんその下の世代に行くにしたがって各世代における男女比の女性割合が増えて、最終的には同じくらいの割合になるということであります。そうした中で、これからますます女性職員の管理職への登用も増えていくだろう思っております。
私自身としては、やはり適材適所、また、能力本位ということで見ています。こうした中で活躍される女性職員の方が非常に多いということで、大変いい傾向だと思っています。
山形新聞社
資料の14ページの【採用】まちづくり政策部都市政策調整監(兼)都市整備部都市政策調整監の樫尾さんは外部からの方でしょうか。
佐藤市長
国土交通省東北地方整備局との人事交流になります。
河北新報
組織改正についてお伺いします。文化スポーツ施設整備室を廃止して、新市民会館とスポーツ施設で分けるというところと、基本構想の策定を受けて日本一の観光案内所の準備室を整備室に変えるということで、山形市で大きなプロジェクトがどんどん進んでいくという印象を受けたのですが、この組織改正で今後どう進めていきたいか、市長の今後の展望をお聞かせください。
佐藤市長
ご指摘いただいた3つの部分につきましては、それぞれのプロジェクトがだいぶ進んでまいりましたので、それに合わせて担当する室をしっかりと準備してあたっていこうということになります。いずれも、戦略的拠点施設といいますか、山形市にとって重要なところでございますので、しっかりと体制を整えながら着実に前に進めていきたいと考えております。
テレビユー山形
東消防署蔵王温泉出張所が新たにでき、インバウンド客や外国人観光客が増える中で救急体制の強化が非常に大きな役割を担ってくると思いますが、こうした救急体制をどのように強靭化していきたいかという所感をお伺いします。
佐藤市長
ご指摘の通り、近年蔵王を訪れる方が外国の方も含めて非常に増えておりますので、この度の蔵王温泉出張所の改築ということで非常に体制強化になると思っております。夏冬問わずトレッキングで山に登る方がおられますし、遭難の事例も出ております。蔵王温泉出張所のハード整備と併せて、山岳で遭難した方をしっかりと救出に向かえる体制の更なる強化をソフト・ハード両面で取り組んでいきます。
(定例)
山形新聞社
発展計画についてお尋ねします。人口減少社会という大きな枠組で見たときに、今年中に山形県全体では100万人割れも見込まれています。その中で、山形市としても、人口が明らかに減っていくという見立てがあると思いますが、それを踏まえて、改めてこの計画をどのように運用していきたいか市長のお考えをお聞かせください。
佐藤市長
持続可能なまちづくりというところに力を入れて、この度発展計画を策定させていただきました。バックキャスティングの手法を取り入れたもの、持続可能性を高めるというところが非常に大きい要素であります。
具体的に、人口減少対策については、できる限り食い止めていくということがまず大切であると思っております。そうした中であらゆる施策を総動員しながら、山形市の魅力を高め、子育て支援をはじめ様々な施策の中でできる限り人口減少を食い止めて、一方で、いわゆる自然減の流れはなかなか一自治体の力だけでは止めきれないところがございますので、そうしたところについては、交流人口の拡大を更に増やしていく。具体的には、観光等に力を入れていく。移住・定住政策にも力を入れていく。関係人口の創出にも力を入れていく。そうした取組がそれにあたると思っております。
また、これからデジタル技術なども更に進歩していきます。そうしたものも活用しながら、山形市が提供している都市機能をできる限り維持していく。そうしたところで人手不足・人口減少に対処しながらしっかりと都市機能を持続していくことが非常に重要だと思っております。例えば、公共交通は自動運転が将来的には非常に大きな要素になるでしょうし、そうしたものを組み合わせながら、人口が減っても元気でいられる山形市をしっかりとつくっていきたいと考えております。
河北新報
発展計画についてお伺いします。公共交通の部分について、仙山圏が一体となって交通網の充実を図っていくという政策を今後発展していきたいということだったと思いますが、現在も仙台―山形の高速バスも頻繁に出ていて仙山線もある中で、今後どういった充実を図っていきたいか展望をお聞かせください。
佐藤市長
仙台市さんとは、行政民間問わずに連携を更に深めて、お互いの往来を更に増やしていく、お互いの都市機能を利用し合って、生活圏として、両市に住んでいる方々がより充実した生活をしていくことが大切だと思っております。
そうした中で、利用者を増やしていくことで本数が増えたり、あるいは収益が上がりその収益を基に公共交通手段を改良していったりという流れにつながっていくものと考えております。仙山線につきましても、仙台市さんと協力しながらより往来を活発にしていく。
また、例えば北山形駅のバリアフリー化などを行わせていただきましたし、今後新駅も作っていくということの中で、鉄道等についても、利便性を高めることで利用者を増やしていく。こうした、やれることをしっかり取り組んでいきたいと考えております。
河北新報
利用者を増やすことで往来が増えるということを期待されているのかと思うのですが、往来が増えると交流人口も増えるという期待を市長が持っていらっしゃるのかお伺いします。
佐藤市長
観光客の方、特にインバウンドの方は公共交通を基本的に利用されます。公共交通の利便性が高まれば、交流人口の方々も移動しやすくなって、さらに旅先としての魅力も高まるということだと思います。公共交通というと、利用者が減ると本数が減って不便になって更に利用者が減るという負のスパイラル、逆に利用者が増えることで収益が上がって本数が増えてより便利になるから利用者が増えるという構造があると思っておりますので、できるだけこの好循環を様々な形で実現できればと思っております。
河北新報
交流人口が増えることで、人口減の食い止めにもつながる効果はどうお考えですか。
佐藤市長
交流人口の増加は、経済の活性化につながるものと考えておりますので、そうした意味では、経済が活性化するとそれに伴って仕事ができる、あるいは山形の企業の収益が上がる、というところにつながってくると思いますので、結果として、人口減少を食い止めることにも寄与すると思っております。
テレビユー山形
発展計画2030の概要・計画策定の考え方の中で「老朽化したインフラ・公共施設への対応など様々な課題が顕在化してくるとされる」とありますが、全国的にも下水道管の老朽化もまだ話題となっている中で、特に山形市としてスピード感を持って対応していかなくてはならないことがあれば教えてください。
佐藤市長
様々なインフラについては、作ってから50~60年経過したものがたくさんございます。道路や橋梁、あるいは学校施設・公共施設など、計画的に長寿命化しながら、しっかりと安全にご利用いただけるよう維持していきます。すでにそうした計画などを立てながらやっているものもありますし、まだ計画ができていないものについても、計画を作って着実に進めていきたいと考えております。
日本経済新聞
市長のビジョンにあります「健康医療先進都市」としての観点から、5年間でこれまでよりさらに突っ込んでいく、次のステージに出ていくというのはどんなところかということを教えてください。
佐藤市長
健康医療先進都市については、かなり幅広い概念ではありますけれども、やはり健康というところで言えば、先般発表させていただいたように、健康寿命が延びたという実績がございますので、これを市民の皆様、あるいは外にもしっかりとPRをして、市民の皆さん自身がその認識を持つことで更に個人の行動変容・健康寿命延伸に向けた生活習慣の改善につなげていきたいと思っております。
これから更に、山形大学医学部などと研究しながらよりデジタルを活用して、デジタルで自分の健康把握・管理に力を入れていければと思っております。
これは世の中がそうした流れに入っていると思いますけれども、アプリ一つとってもたくさんある中で、どういったものが効果的なのかということを常に検証していきながら、よりそうした部分を強化することで健康医療先進都市に更に近づいていきたいと考えております。
日本経済新聞社
そうした流れで言いますと、健康ポイント事業SUKSKは非常に大きなツールであるということでしょうか。
佐藤市長
既に登録者数も17,000人を超え、かなり増えてきておりますので、まさに1つのプラットフォームになっているものと思っております。
これからの新たな健康医療施策についてもそこと絡めながら、ご利用いただいている方は健康についての意識がすでにおありな方が多いと思いますので、そうしたところで更に生かしていければという風に思っております。
山形放送
「日本一の観光案内所準備室」を「日本一の観光案内所整備室」に設置していますけれども、改めて、今の地権者との協議の段階や現在地、今後の見通しで決まっているものがあればお伺いしたいです。
佐藤市長
現在、地権者の方との最終的な詰めの段階という状況でございます。そうした協議が整い次第また改めて発表させていただきたいと思っております。
実際には、地権者の中で面積を占めている方がホテルのグループということですので、ホテルが建って、そして1階・2階を市が借り受けて観光案内所にしていく。ペデストリアンデッキから直結した形で、山形駅を降りたらまず来ていただく場所にしたい、という方向で協議を進めているということであります。
山形放送
観光案内所の整備について、地権者の方の感触としてはどのような印象でしょうか。
佐藤市長
概ね方向性についてはご理解いただいておりますので、今、最終的な実務的な詰めをしているとご理解いただければと思います。
共同通信社
発展計画についてお伺いします。先ほどの質問の中で、選ばれるまちにするため都市機能を維持することが重要とのお話がありました。都市機能を維持するという観点から、先ほどの自動運転のお話のように具体的に進めていきたいことをいくつか例示するとすれば、どのようなものがありますでしょうか。
佐藤市長
都市機能については様々な要素がございますけれども、公的な要素が強いものとしては医療と教育だと思います。まず医療につきましては、以前から申し上げておりますとおり、山形市は他のエリアと比較すると非常に充実した医療資源がありますので、そこをしっかりと維持していくことが大切だと思っております。
そうした中で、病院も経営が大事だと思いますので、市立病院済生館も村山地域一円から来ていただける運営をしていかなければと思っておりますし、医師の確保につきましても山大医学部等、あるいは県と連携しながらしっかりと維持できるように、市としてできることをやっていくということだと思います。
また、重粒子線治療をはじめ、外から来ていただけるような資源もございますので、そうしたところもよりPRしていきたいと考えております。また教育につきましても、山形市は、小・中・高、大学と充実した資源がございます。市としては、義務教育という部分を担っておりますので、今進めております教育のデジタル化や部活動の地域移行などの課題にしっかりと取り組んで、子どもさんを安心して預けていただける学校づくりを山形市として更に進め、魅力を高めていきたい。そんな取組をしながら都市機能を維持していきたいと考えています。
共同通信社
医療と教育の分野というものについても、デジタルの力を十分に活用していくということでよろしいでしょうか。
佐藤市長
教育については先ほどデジタル化についてお話ししましたけれども、医療等につきましても、これから在宅での診療や遠隔でということも出てくると思います。ですので、そうしたものにも対応し、自分の住んでいる近くの方以外の方に、どうやって広げていくかということが、全体として人口減少が進む中で重要であると思っておりますので、その当たりの取組も大切だと思っています。
テレビユー山形
宿泊税についてお伺いします。今月の市議会で宿泊税について問われるシーンがあり、市長は前向きにスピード感をもって進めていきたいというような発言をしていらっしゃいましたが、山形市はインバウンド客も多く訪れるので、税収も見込める非常に関心度の高いことだと思います。改めて、宿泊税の導入向けた市のお考えをお聞かせください。
佐藤市長
発展計画で示した通り、観光をこれから更に力を入れていきたいと思っておりますし、私自身も観光については非常に伸び代が大きいと思っております。日本一の観光案内所をはじめ、千歳館、御殿堰の更なる延伸、粋七プロジェクト等のまちなか観光に資する様々なプロジェクトが同時並行的に進めているところであります。それを更に加速していくためには、観光で来て泊まっていただく方から宿泊税という形でいただいて、それを財源として更に取組を進め、更に宿泊してくださる方を増やしていくことが大きな目的だと思っております。
既に全国多くの市が取り入れておりまして、東北においても最近では仙台市や弘前市が導入に向けてかなり動いているというところです。山形市としてもこれまで内部的な検討をし、いろんな調査を行いました。こうしたものを基に、これからは実際に手続き等でお力をいただかなければならない市内の宿泊事業者の関係者の皆様としっかり意見交換しながら導入に向けて歩んでいきたいと考えております。宿泊事業者の皆さん、行政、市民、観光客の方、みんながウィンウィンになるような形の導入を目指していきたいと考えております。
テレビユー山形
市内の宿泊事業者との話し合いなど今後のスケジュールは決まっていますか。
佐藤市長
そんなに遠くない時期にまずお会いして、キックオフと言いますか、1回で終わるものではないと思いますので、課題などを整理して解決に向けて話し合いを進めていくということになると思います。これは本当にすぐ行っていきたいと思っています。
テレビユー山形
市としてはどれくらいの税収を見込んでいて、どんな展望があるのか、期待値を教えてください。
佐藤市長
これについては、定額制にするか定率制にするかというように、いろいろなやり方があります。定額にしてもいくらにするか、あるいは宿泊料によって段階を設けるかなど様々なやり方によって全然変わってきますので、今このくらいというものは申し上げられませんけれども、数億円のイメージかなと思っています。
河北新報
今月、東北新幹線と秋田新幹線の連結部分が外れてしまい、一時期山形新幹線も福島までの運行になりましたが、今後このようなことがないようにJRさんへ要望するようなことがあればお伺いしたいです。
佐藤市長
その件につきましては、国土交通省の方でJR東日本さんに対して指導や原因究明の動きがあると思いますので、山形市として更に要望することは考えておりません。検証をしっかり進めていただければと考えております。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部秘書課秘書係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線200・202・207
ファクス番号:023-624-9888
hisyo@city.yamagata-yamagata.lg.jp