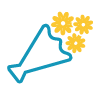腸管出血性大腸菌(О157)感染症の集団発生の状況及び注意喚起について
山形市内において、腸管出血性大腸菌(О157)感染症の集団発生が確認されましたので、お知らせします。
詳細はこちらの資料をご覧ください。
腸管出血性大腸菌感染症とは
家畜や人の腸内にも存在する大腸菌のほとんどは無害ですが、いくつかのものは下痢等の消化器症状や合併症を起こすことがあり、病原大腸菌と呼ばれています。病原大腸菌の中には、毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群(HUS)を起こす、腸管出血性大腸菌と呼ばれるものがあります。
腸管出血性大腸菌は、菌の成分によりいくつかに分類され、代表的なものとして「О157」「О26」「О111」等が知られています。牛等の家畜や人の糞便中に時々見つかりますが、家畜では症状を出さないことが多く、見ただけでは菌を保有する家畜かどうかの判別は困難です。
感染経路
- 家畜や感染者の糞便により、菌に汚染された食品・食器・手指等を介して口から感染します(経口感染)。100個程度の菌数でも感染すると言われており、感染力が強い点が特徴です。
- 職場や学校での会話や、咳・くしゃみ等の飛沫では感染しません。
- 国内では、井戸水・牛肉・ハンバーグ・サラダ(生野菜)等による感染が報告されています。
- ふれあい動物イベントや搾乳体験等を原因とする感染事例の報告もあり、家畜の糞便により汚染された小動物の体表をから二次的に人が感染を起こす可能性もあります。
主な症状
- 症状には個人差がありますが、激しい腹痛や水様性の下痢、血便を特徴とします。
- 特に抵抗力の弱い小児や高齢者では、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症(けいれんや意識障害等)等の重篤な合併症を引き起こしやすく、注意が必要です。
- 感染しても無症状のまま経過することもありますが、症状がない感染者からも感染が起こるおそれがあるため、手洗い等の感染対策をしっかり行うことが重要です。
感染予防のために
1 菌をつけない
- 食事や調理の前、トイレやおむつ交換の後、動物に触れた後、外出先からの帰宅後は、石けんと流水でよく手を洗いましょう。
- 生で食べる野菜と、加熱が必要な肉類等の調理は分けましょう。まな板や包丁はそれぞれ使い分けると安全です。
- 生野菜を食べる際はよく洗いましょう。
2 菌を増やさない
- 購入した食品は、肉汁や魚等の水分が漏れないようにビニール袋等に分けて包み、持ち帰りましょう。
- 消費期限等をよく確認して購入しましょう。
- 生鮮食品等、冷蔵や冷凍による温度管理が必要な食品の購入は買い物の最後に回るようにする、帰宅後は速やかに冷蔵庫へしまう等を心掛けましょう。
3 菌をやっつける
- 中心部までよく加熱しましょう。目安は75℃で1分以上の加熱です。
- バーベキューや焼き肉、しゃぶしゃぶ等を食べる際には、肉を焼く時と食べる時とで別々の箸を使用しましょう。
- 調理器具(まな板・包丁・ふきん・スポンジ等)を清潔に保ち、必要に応じて熱湯や漂白剤で消毒を行いましょう。
参考
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康医療部精神保健・感染症対策室感染症予防係
〒990-8580
山形市城南町一丁目1番1号霞城セントラル4階
電話番号:023-616-7274
ファクス番号:023-616-7276
seishin-hk@city.yamagata-yamagata.lg.jp