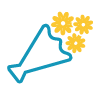児童扶養手当(ひとり親等に係る手当)について
制度概要
児童扶養手当制度は、父母の離婚などの理由により父または母と生計を同じくしていない児童のいるひとり親家庭等の保護者の方へ手当を支給し、生活の安定と自立の促進を通じて児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当を受けることができる方
次の1から9のいずれかに該当する児童(18歳になった年度末まで・心身に一定の障がいを持つ児童については20歳未満)を養育している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
- 父と母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父・母とも不明である児童
※申請者または配偶者もしくは児童が公的年金等を受給する場合は、1ヵ月あたりの公的年金受給額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金の受給額が児童扶養手当の金額を上回る場合は、手当は支給停止となります。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
児童に関する要件
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 児童福祉施設に入所しているときなど、受給者が養育していると認められないとき
- 受給者以外の父または母と住所・生計が同じとき※父または母が重度の障害の場合を除く
- 父または母の配偶者(婚姻していなくても、異性と同居する等の事実婚状態を含む)に養育されているとき ※父または母が重度の障害の場合を除く
父母又は養育者に関する要件
- 日本国内に住所を有しないとき
- 配偶者(婚姻していなくても、同居の事実婚を含む)と生活をともにしているとき(受給者が父または母の場合)※父または母が重度の障害の場合を除く
手当月額(令和7年4月分から)
※月額は、受給者の所得に応じて決定されます。
※一部支給については、年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額が細かく設定されています。
| 対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人目以降 | 11,030円を加算 | 対象児童一人につき11,020~5,520円を加算 |
所得の制限
この手当は、受給者や同居している扶養義務者の前年の所得(1~9月に請求する場合は前々年度の所得)に応じて決定します。下記の表の限度額を超えている場合は、手当の一部または全部が支給されません。
所得制限限度額表
令和6年11月分の手当(令和7年1月支払分)から、所得制限限度額が下記のとおり引き上げられました。
※孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者については変更はありません。
| 税金上の扶養親族等の数(人) | 申請者(受給資格者) | 孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | |||||
| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
| 0 | 1,420,000 | 690,000 | 3,343,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
| 1 | 1,900,000 | 1,070,000 | 3,850,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
| 2 | 2,443,000 | 1,450,000 | 4,325,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
| 3 | 2,986,000 | 1,830,000 | 4,800,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
| 4 | 3,529,000 | 2,210,000 | 5,275,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
| 5 | 4,013,000 | 2,590,000 | 5,750,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
申請者(受給資格者)や扶養義務者(住所を同じくする申請者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1~9月に申請する場合は前々年の所得)により児童扶養手当の支給額が決定されます。
所得制限限度額は、申請者(受給資格者)と扶養義務者等によって異なり、対象年度における所得税法上の扶養人数によって異なります。
また、扶養義務者等の所得が「孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者」欄の所得制限限度額以上の場合は全額支給停止となります。
※申請者(受給資格者)については老人扶養1人につき10万円、特定扶養等1人につき15万円が限度額に加算されます。
※申請者(受給資格者)の所得には、養育費を受け取っている場合、その8割が加算されます。
※孤児等の養育者/配偶者/扶養義務者については、老人扶養1人につき6万円が限度額に加算されます。(扶養親族等が70歳以上の場合は1人を除く)
支給時期
支払は、下記の支払日に支払月の前月分までの手当額を受給者の指定した金融機関の口座(請求者名義に限る)へ振り込みます。
| 支給日 | 対象月 |
|---|---|
| 1月11日 | 11、12月分 |
| 3月11日 | 1、2月分 |
| 5月11日 | 3、4月分 |
| 7月11日 | 5、6月分 |
| 9月11日 | 7、8月分 |
| 11月11日 | 9、10月分 |
※支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支給日となります。
※転出や受給者の変更などの理由により、支給日が異なる場合があります。
手当の申請手続き(認定請求)
手当を受給するには、ご本人による申請手続きが必要です。手当額は、申請した月の翌月分からの支給となります。
受付窓口
市役所2階10番窓口 こども家庭支援課(午前8時30分~午後5時15分)
申請に必要なもの
1. 申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本、1か月以内に発行のもの)
※月末に離婚届を提出し、戸籍全部事項証明書への離婚日の記載が月をまたぐ場合は、「離婚届受理証明書」で申請を受け付けることができます。ただし、後日、離婚日の記載がある戸籍全部事項証明書の提出が必要となります。
2. 申請者名義の銀行通帳またはキャッシュカード
3. 年金手帳または基礎年金番号通知書
4. 本人、児童および同居の家族のマイナンバーカード
(または個人番号通知書(通知カード)および申請者の運転免許証等の身元確認書類)
※その他、上記のほかに必要書類がある場合がありますので、詳しくはお問合せください。
認定を受けた方について
現況届
児童扶養手当受給資格の認定を受けた方は、前年の所得状況と児童の養育状況等を確認するために、毎年8月に現況届(更新手続き)を提出する必要があります。現況届の提出は、代理人や郵送では受付できませんので、必ず窓口にてお手続きください。
毎年8月1日~8月31日(土曜・日曜・祝日除く)の間に現況届を提出していただかないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
また、現況届が2年以上未提出の場合は、時効によって受給資格が喪失しますのでご注意ください。
なお、所得制限限度額以上により手当の支給がなかった方も、受給資格の更新のため現況届の提出が必要となります。
一部支給停止適用除外事由届出
児童扶養手当を申請されてから5年経過等に該当する方は手当額の2分の1が減額になります。
ただし、就業しているなど、下記の「適用除外事由」に該当し、期限内に届け出をしていただくと、その年度の手当を減額されずに受給することができます。
- ※対象の方には事前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と案内、必要書類を一緒に送付しますので、内容をご確認のうえ届出書と必要書類を提出してください。
- ※この届出は現況届と一緒に8月中に提出していただきます。対象になる場合、毎年届け出が必要となります。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 手当の支給開始月から5年を経過した方
- 手当の支給要件に該当するに至った日(離婚日など)から7年を経過した方
※ただし、手当の認定請求をした日において対象児童が3歳未満の場合は、児童が3歳に達した日から5年を経過したときに対象となります。
適用除外事由
次のいずれかに該当する場合は、その状態を明らかにする書類を添付のうえ手続きをしていただいて手当を減額されずに受給することができます。
- 就労している場合
- 求職活動をしている場合
- 受給者が一定程度の障がい状態にある場合
- 受給者が負傷および疾病等で就労困難な場合
- 受給者が監護する児童や親族が疾病及び障がいで要介護状態にあることにより、就労が困難な場合
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部こども家庭支援課手当係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線558・575
ファクス番号:023-624-8901
kodomofukushi@city.yamagata-yamagata.lg.jp