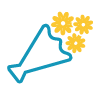一般質問(令和7年9月定例会)
令和7年9月定例会で行われた一般質問は、以下のとおりです。
(ここに掲載した一般質問は、市議会報234号に掲載したものを再掲載しており、質問内容は実際の質問を要約・抜粋したものです。)
【高橋 公夫 議員】避難所に「快適トイレ」の 整備を
避難生活での精神的負担などが原因の災害関連死を防ぐため、簡易トイレの配置などの避難所の環境整備にどのように取り組んでいくのか。
(回答)令和7年度に避難所等環境整備計画を策定し、不足する資機材の計画的な確保に向けて取り組んでいくとともに、災害関連死ゼロに向けて改善を進めていく。
災害時の避難所環境の向上と建設現場の労働環境の改善のため、快適トイレの整備を行う民間事業者へ補助を行ってはどうか。
(回答)建設現場の仮設トイレの大半はレンタルでの調達品であるため、市と災害協定を締結しているレンタル事業者と、快適トイレの確保に向けた意見交換を実施していく。
フリースクールなどの運営経費への補助や、不登校児童・生徒が安心して過ごせる学校外の居場所の確保に向けた取り組みはどうか。
(回答)令和7年9月定例会に、フリースクールの利用者を支援するための補正予算を計上しており、運営団体の意向などを踏まえた効果的な支援を検討していく。また、個々のニーズに応じた学校外の多様な居場所づくりを、今後も調査研究していく。
総務省消防庁のモデル事業を活用し、消防団員を対象としたドローン操縦者養成研修を行ってはどうか。
(回答)ドローンの導入や運用は、大規模な災害時での活用や消防団への加入促進などにも効果的であることから、消防団と活用を検討していく。
消防関連施設や新設する市の施設などに、消防団をPRするデザインの自動販売機を設置し、売り上げの一部を消防団の装備の購入費に充てることで、消防団の支援と認知度向上を図ってはどうか。
(回答)入団促進や装備の充実につながる手法の一つと考えており、民間事業者からの協力を得た消防団の認知度向上手法と、消防団への資金面での支援手法などを検討していく。
冬季の観光資源として啓翁桜の見学ツアーを実施するなど、インバウンド向けのプロモーションやツアー造成を行ってはどうか。
(回答)旅行会社と連携したツアーの造成など、観光資源としての活用も見据えて取り組んでいく。また、啓翁桜を取り入れた体験メニューの実施は、山形市グリーンツーリズム振興協議会で地域団体などと検討していく。
蔵王駅の機能強化や利便性向上などのため、西口や東西自由通路の整備をJR東日本に働きかけてはどうか。
(回答)JR東日本をはじめとする関係機関との意見交換を継続するとともに、地区からの要望も踏まえて、実現の可能性を探っていく。
【鈴木 進 議員】みんなで考える 地域の安心とつながり
地域共生社会の実現を推進する認知症施策推進計画の策定に向けた状況はどうか。
(回答)認知症の当事者の声を聞きながら、当事者と家族の視点を尊重した計画とする予定であり、策定過程も含めた検討を進めている。
令和7年3月に地域住民を対象に実施した(仮称)北くるりんの利用意向調査アンケートの結果はどうか。
(回答)1502世帯からの回答のうち、約6割が利用に関心があった。また、馬見ヶ崎地区周辺のスーパーや病院への移動の需要が高く、分析やモデル事業の結果、今後の説明会での意見などを踏まえて、運行方法を検討していく。
学校の体育館での避難生活は気候の影響を受けやすいため、教室などの利用は学校長の個別判断ではなく、市が統一的に判断することにしてはどうか。
(回答)避難者の安心安全の確保に有効であるため、令和7年度の避難所等環境整備計画の策定と併せて検討していく。
岩手県滝沢市では、小中一貫で水泳指導の見直しを行い、救命措置の学習に重点を置く取り組みを進めている。本市でも水泳授業の在り方を見直してはどうか。
(回答)学習指導要領上、学年ごとに指導内容が定められており、水泳授業は必要と考えているが、民間施設の活用も含めた水泳授業の在り方を引き続き検討していく。
市内中心部の小学校では児童数の減少が顕著となっているが、今後の施設整備に併せた学校統合や通学区域の見直しは検討していくのか。
(回答)地域との協働のもとで最善の教育環境を提供するため、現時点では学校配置の維持を基本的な方向性としている。
給食は、成長期の児童・生徒の栄養管理面を考慮した、十分な内容になっているのか。
(回答)栄養素が強化された食品の使用や残食を減らすための食材選定を行っており、栄養指導などを継続することで、食への正しい理解と判断力を養えるように努めていく。
河川の藪がクマの移動経路となっている可能性が高いため、河川管理者である国や県と早急に連携し、対策を推進すべきではないか。
(回答)県に河川の藪の刈り払いを緊急要望しているほか、河川一斉清掃や河川パトロールの強化など、効果的な取り組みを実施していく。
身体障がい者や高齢者が市有施設のすべての出入り口を利用できるように、手すりの設置やスロープ形状への改修などを行ってはどうか。
(回答)市有施設安全点検の項目にバリアフリーの観点を追加し、施設の安全性と利便性の確保に努めていく。
【井上 和行 議員】高齢者の移動支援・運転免許証返納促進策の拡充を!
運転免許証自主返納者へのタクシー券の交付は、一括での交付と、少額での継続交付の選択制としてはどうか。
(回答)令和7年度交付分から使用期限を延長したため、効果を確認し、さらなる有効活用に向けた課題を検証していく。
認知症高齢者が原因となる交通事故が社会問題化しているため、本市が保険料を負担する事故補償保険制度を導入してはどうか。
(回答)当事者団体や関係機関の意見を聞きながら他市の事例も参考に検討していく。
夏季に小・中学校体育館が避難所となった場合の環境改善対策と冷房設備の整備計画の検討状況はどうか。
(回答)より早期に空調設備を整備できるように検討するとともに、7年度に策定する避難所等環境整備計画の中で、熱中症予防のための備品の拡充などを検討していく。
障がい者の避難行動の迅速化を図るため、福祉避難所に直接避難できる仕組みを整備してはどうか。
(回答)新たな福祉避難所の設置に向けて、特別支援学校などとの協議を進めるとともに、障がい特性などに応じた受け入れ体制を構築していく。
FIS女子スキージャンプワールドカップ蔵王大会の費用対効果などを検証し、運営の在り方を議論すべきではないか。
(回答)幅広く意見を聞きながら慎重に検討していく。
小学校のスキー教室実施に伴う保護者負担の軽減を図るとともに、指導体制の整備など、高学年でも実施できる環境の整備を行ってはどうか。
(回答)スキー教室への支援を継続しながら、各学校への補助額の増額や環境整備を研究していく。
県と市が共同で整備を進めている屋内スケートリンクも含めた新スポーツ施設の協議状況はどうか。
(回答)7年度は検討会議を2回開催しており、県体育館・武道館の利用者がしっかりと利用できる施設になるように、県と協議を行っている。
地域建設業の健全な維持・育成や、持続可能な公共インフラの整備・維持管理に向けて、建設関連予算を確保することが重要ではないか。
(回答)建設関連予算を含め、幅広い分野への物価高騰の影響に対応しながら、持続可能な行政運営の推進に向けて、トータルでバランスの取れた予算編成に努めていく。
米の安定供給の確保や生産者の持続的な営農支援のため、どのような取り組みを検討しているのか。
(回答)スマート農業の中山間地域での活用の実証や農業機械導入への支援策などの拡充を検討していく。
【髙橋 康輔 議員】若者に身近な施策で まちの魅力を高めよう
業務体験型の不登校支援を実施し、図書館での仕事体験を出席扱いにするなど、多様な居場所づくりに取り組んではどうか。
(回答)他市の事例を参考に、学校と地域社会が連携した、子どもが安らぐ居場所づくりを調査研究していく。
本に触れる機会の創出や外出支援のため、移動図書館を導入してはどうか。
(回答)本のひろばの開設や電子書籍サービスの導入に向けた準備などを継続し、サービスの充実を図るとともに、市民ニーズの把握に努めていく。
町内会がSNSなどを活用して情報発信できるように、支援を行ってはどうか。
(回答)スマホ講座の案内や、操作説明などを行っており、希望に応じた必要な支援に取り組んでいく。
東京都豊島区の子どもレターを参考に、子どもの意見を市政に反映させるための取り組みを行ってはどうか。
(回答)山形市こども計画では、子どもや若者の意見を聞いて施策に反映させるための仕組みを構築することとしており、先進自治体の取り組みも研究しながら検討していく。
クーリングシェルターに指定している市有施設に、マイボトル用の給水器を設置してはどうか。
(回答)熱中症予防とプラスチック削減に効果的であるため、導入事例を調査研究していく。
ゼロカーボンシティ実現のため、太陽光発電や蓄電池の普及に向けて、どのように取り組んでいくのか。
(回答)太陽光発電設備などの導入や省エネ高効率設備への更新などに支援を行っており、脱炭素化と災害に強いまちづくりを進めていく。
小・中学校の防犯設備の整備状況と、教職員の不審者対応の訓練状況はどうか。
(回答)令和7年度に全小・中学校への防犯カメラとオートロックの設置が完了する予定である。また、各学校で作成した危機管理マニュアルに沿って訓練を実施しており、関係機関と連携した効果的な防犯体制の確立に努めていく。
消防団員の確保のため、学生を対象とした機能別消防団を設置するなど、制度を拡充してはどうか。
(回答)学生の消防団入団は課題もあるが、有資格者が活躍できる機能別消防団の構築を、消防団と検討していく。
労働条件をめぐるトラブル防止や人材の定着などを図るため、社会人になる前に労働法の知識を身に付けられるように、高校や大学への出前講座を実施してはどうか。
(回答)労働局や県の取り組みを周知するとともに、学校や関係団体との連携を図りながら、若者が安心して社会に踏み出せるように支援していく。
【小野 仁 議員】「最上踊り」を山形城でもう一度!
県と連携し、カード型の障がい者手帳を導入してはどうか。
(回答)当事者の意見を聞くとともに、他自治体の取り組みも参考にしながら、県と連携して検討していく。
ひきこもり支援のための条例制定に向けた進展状況はどうか。
(回答)支援機関などと構成するひきこもり支援検討会を開催し、令和7年度内の条例制定を目指して作業を進めている。
さまざまな困難を抱える難病患者や家族を支援する団体が充実した活動を行えるように、補助を行ってはどうか。
(回答)県と情報を共有しながら必要な対応を検討し、患者本人や家族が社会から孤立することなく安心して暮らせる環境づくりに努めていく。
SUKSK生活を提唱し、禁煙を推奨する一方で、賑わい創出のためのイベントなどに喫煙ブースを設置しているが、整合性は取れているのか。
(回答)分煙施設周辺での注意喚起など、市民や来訪者が安心して快適に過ごせる環境づくりを進めていく。
山形美術館では、民間企業から寄託されていた絵画を返却することとなったが、市はどのように対応していくのか。また、今後、施設全体の設備更新が必要となった際には、補助を拡充してはどうか。
(回答)文化創造都市を推進する上で重要な拠点と考えており、これまでも運営費の補助などを行っているが、協力の在り方を協議していきたい。
最上踊りが伝承されている滋賀県東近江市との相互交流を行ってはどうか。
(回答)最上踊り保存会の活動状況を把握し、意向を確認しながら、交流の在り方などを研究していく。
小・中学校校舎の建て替えを検討する際の「老朽化」の定義はどうか。
(回答)経年のため施設・設備の機能が低下することを老朽化と捉えており、現在改定作業を進めている小中学校施設整備方針などで、改築などの考え方を整理していく。
公正性・透明性の確保などのため、プロポーザル方式での事業者選定の手法を見直すべきではないか。
(回答)6年度に公民連携室を設置し、ルールなどを整理して契約手続きへ反映させている。他自治体の例を参考にしながら、今後も公正性・透明性の確保に努めていく。
ボウリング競技は年代や性別を問わず楽しめる生涯スポーツであるため、競技場の運営へ支援を行ってはどうか。
(回答)ボウリング競技以外も含め、大会開催団体などに支援を行っており、より良い支援のために調査研究していく。
【仁藤 俊 議員】稼げる自治体・収益化できるまちづくりを
インバウンド旅行客が増える中、観光業界の収益化に向けた今後の方向性はどうか。
(回答)海外への観光プロモーションの推進や、観光客の利便性や満足度を高めることで、観光産業が基幹産業となるように努めていく。
山寺を訪れた観光客が市内のほかの地域も周遊するための仕組みづくりを、どのように考えているのか。
(回答)プロモーションやコンテンツの充実などを図るとともに、蔵王や中心市街地も周遊できる仕組みづくりに取り組んでいく。
蔵王の魅力を最大限に活かし、持続可能な通年性のある観光地にするため、どのような戦略を講じていくのか。
(回答)蔵王のさまざまな観光コンテンツを道の駅やまがた蔵王や山形駅の観光案内所で周知するなど、さらなる誘客推進につなげていく。
大手総合リゾート運営会社での運営が見込まれている蔵王温泉の宿泊施設と、どのように関わり、蔵王の活性化を図っていくのか。
(回答)蔵王温泉観光協会などと連携し、相乗効果を生み出せるように、可能な範囲で連携した取り組みを行っていく。
義光祭を復活し、大河ドラマ誘致に向けた機運を高めてはどうか。また、誘致に向けた状況はどうか。
(回答)義光祭の復活は、関係団体などの意見を聞きながら研究していく。また、大河ドラマ誘致の調査検討を行っており、最上義光を大河ドラマにする会と情報を共有しながら活動に協力していく。
旧千歳館エリア活性化計画の今後の展開と、粋七エリアとの関連性や回遊性をどのように考えているのか。
(回答)古民家カフェや分散型ホテルなどの機能を創出し、日中も楽しめるまちを目指すとともに、粋七エリア整備事業などと連携して、一体となって魅力向上につなげていく。
粋七エリア整備事業などを進める中で、諏訪町七日町線沿いの旧料亭の桜や庭を、どのようにまちづくりに活かしていくのか。
(回答)桜などの景観資源を公共空間に融合させることで、さらなる魅力を創出していく。
ほっとなる広場公園のPark-PFIでの再整備を検討し、移動式店舗などを導入できるようにしてはどうか。
(回答)公園の新たな利活用などを検討しており、近隣商店街の意見を聞きながら移動式店舗の導入も検討していく。
騒音とフン被害を防ぐため、鷹匠を招いたカラス対策を早急に実施してはどうか。
(回答)樹木剪定やごみの適正管理など、生息環境の改善とともに総合的に取り組んでいく。
【武田 新世 議員】安全・安心な環境を整備し 多様性を尊重する社会の構築を
適切に管理されずに周辺地域の環境に悪影響を与える空き家の発生を抑制するとともに、適切な管理の促進が必要ではないか。
(回答)適正管理依頼文書の送付のほか、民間事業者と連携した空き家相談会の実施など、所有者の意識と理解の向上を図っている。町内会や民間事業者と連携しながら、空き家の適正管理に努めていく。
児童や生徒が安全・安心に学べる環境の整備と、避難所としての生活環境向上のため、学校体育館に冷房設備を早期に導入すべきではないか。
(回答)令和15年度までに全小・中学校へ計画的に整備することとしているが、ほかの大規模事業との兼ね合いなどを考慮し、先行自治体の取り組みを調査研究しながら、国の動向も注視して早期に整備できるように検討していく。
少年自然の家は児童・生徒に生涯学習の機会を提供する重要な拠点施設であるため、快適性や衛生面などを考慮し、トイレの洋式化を早期に進めるべきではないか。
(回答)幅広い層が楽しめる持続可能な施設への転換を目指し、基本計画案の取りまとめ作業を行っている。本館トイレの洋式化など、利用者のニーズを捉えた改修を行う予定であり、基本計画策定の進展を踏まえて、早期の改修が可能か検討していく。
国道13号から流通団地への進入口は、逆走などの恐れがあるため、看板を設置して注意喚起するなど、道路環境を整備してはどうか。
(回答)分かりやすい場所へ道路標識を移設するなどの交通規制を警察署に要望するとともに、国道の道路管理者と協議しながら、看板設置などの事故防止策を検討していく。
日本一の観光案内所に、アクセシブル・ツーリズム対応窓口を設置してはどうか。
(回答)現在策定中の基本計画でも、バリアフリーやユニバーサルデザイン、インクルーシブデザインの考えを基にした多様な利用者への考慮を留意点の一つとしており、より多くの人が快適に利用できるサービスの充実を目指していく。
移住促進と併せて、今後ニーズが高まると予想される二地域居住への支援にも取り組んでいくべきではないか。
(回答)二地域居住の促進で国の支援を受けるためには、県が広域的地域活性化基盤整備計画を策定し、市が特定居住促進計画を作成する必要がある。今後、県との情報交換に努めながら、動向を注視していく。
民間企業と連携して家庭や店舗などの廃食油を回収し、SAFとして航空機の燃料に活用してはどうか。
(回答)循環型社会の推進や脱炭素社会の実現に有効であると認識しており、国の動向や先進自治体の事例を注視し、民間事業者と情報交換を行いながら、実現の可能性を調査研究していく。
【浅野 弥史 議員】県設置の屋内型スケート施設の必要性は十分に 議論されていますか?
霞城公園の整備が進んでいるが、今後も霞城公園で花火大会を開催できるのか。
(回答)霞城公園での打ち上げが継続できるように、関係団体と協議しながら整備していく。
県が数十億円の整備費をかけて市内に屋内型スケート施設を建設する予定だが、本市の考えはどうか。
(回答)多機能性を有する屋内スケート施設を県が整備することで、令和6年10月に県と合意している。まだ充足されていない市内の屋内多目的施設は、全体的な施設の配置や稼働状況などを調査分析した上で整備の検討を行っていく。
利用世帯数の減少や高齢化が進む中、簡易水道の今後の維持管理や更新をどのように考えているのか。
(回答)水道組合ごとに条件が異なるため、個別に状況を聞きながら、検討していく。
部活動地域展開に取り組む上で、地域クラブへの学校施設の開放は行うのか。
(回答)これまで部活動で使用していた時間帯は、市が認定する地域クラブが屋内・屋外運動場を優先的に使用できる方向で検討を進めている。
総合評価落札方式での工事入札を増やしてはどうか。
(回答)建設業界と意見交換する中で課題を共有しながら、適切な運用方法を検討していく。
改正鳥獣保護管理法が施行され、市町村長の判断で人の日常生活圏での危険鳥獣の銃猟が可能になったが、どのように取り組んでいくのか。
(回答)警察やアーバンベア等対応チームなどと連携し、銃猟実施の判断や役割分担を平時から確認するとともに、実際の銃猟時の確実な連携のために、訓練や研修を重ねていく。
コミュ二ティセンターなどの市有施設に、リチウムイオン電池の回収ボックスを設置してはどうか。
(回答)より身近な場所で利用できるように、コミュニティセンターなどの市有施設への設置の拡充を検討していく。
障がい者等日常生活用具給付等事業で給付対象となっている特殊マットや移動用リフトの補助基準額を見直してはどうか。
(回答)利用者のニーズを踏まえて、他市の状況を参考にしながら見直しを検討していく。
診療報酬が上がらない状況では済生館の大幅な増益は期待できない上、建設費に見合う国からの補助も見込めないが、建て替えに向けた今後の見通しはどうか。
(回答)基本設計を2段階に分割し、前編業務として、病院設計の豊富なノウハウを持つ事業者のアイデアを取り入れながら、必要な機能を満たしつつ可能な限りコスト縮減を図るための方策を、十分に検討していく。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-642-8404 ファクス番号:023-641-9160
giji@city.yamagata-yamagata.lg.jp