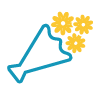一般質問(令和6年12月定例会)
令和6年12月定例会で行われた一般質問は、以下のとおりです。
(ここに掲載した一般質問は、市議会報231号に掲載したものを再掲載しており、質問内容は実際の質問を要約・抜粋したものです。)
【渋江 朋博 議員】ベニちゃんバスの安全・安心な運行を目指せ!
ベニちゃんバスの車両の劣化が懸念されることから、増台を検討してはどうか。
(回答)車両の更新時期を見極めながら、計画的な更新に努めるとともに、増台も検討する。
本市でもカスタマーハラスメント防止条例を制定してはどうか。
(回答)国の審議会では、カスタマーハラスメント対策を事業主の雇用管理上の措置義務とする議論が行われているため、国の動向を注視しながら先進事例などを調査研究していく。
学校給食費の無償化を本市単独で行ってはどうか。
(回答)就学援助受給世帯などの無償化は行っているが、食材費高騰に対する財政支援の継続などを国へ要望していく。
スワンヒル地方市との短期交換留学事業が6年ぶりに実施されるが、家庭の経済状況で体験格差が生じないように、派遣生への支援を行ってはどうか。
(回答)派遣生に6万円の激励金を支給することとしているが、他自治体の状況を参考にしながら支援内容を検討していく。
国は地方創生交付金の対象にトイレカーなどの防災備蓄品を含める方針であるため、本市も導入を進めてはどうか。
(回答)令和6年能登半島地震での課題を踏まえて、令和7年度に避難所・避難場所環境整備計画を策定する予定であり、トイレカーの導入なども併せて検討する。
自治会活動の負担となっている広報やまがたの配布を民間へ委託してはどうか。
(回答)配布謝礼が町内会・自治会の収入源となる場合もあることから、慎重な検討が必要であるが、負担軽減に向けて、配布回数の削減などの見直しを進める予定である。
町内会・自治会向けポータルサイトの構築や機器導入への補助を行い、自治会のDX化を推進してはどうか。
(回答)ポータルサイトは、申請手続きの簡素化などのメリットがあるが、急速なデジタル化への不安などにも配慮し、先進自治体の取り組みも参考にして調査研究していく。
盃山展望台の周辺は、生い茂った木々で景色が全く見えないため、親しまれる展望台として整備してはどうか。
(回答)4年度に木々の伐採を検討したが、地権者の同意や国道13号の交通規制が必要となるなどの理由で、実施に至らなかった。今後は枝払いなどを行い、眺望を確保していく。
小白川街道の無電柱化に向けた議論の方向性が見えないとの意見もあるため、市が具体案を示すべきではないか。
(回答)勉強会や現地視察を行うなど、地域の理解を得た上で事業が進められるように丁寧な説明を継続していく。
【阿曽 隆 議員】介護事業所へ市独自の支援策を!!
介護報酬改定に伴い訪問介護事業の基本報酬が減額されたが、減額の撤回と報酬の引き上げを国に求めてはどうか。また、光熱水費やガソリン代への補助など、市独自の支援を行ってはどうか。
(回答)訪問介護事業所が安定したサービスを提供するため、必要な支援を行うように全国市長会から国へ要請している。国では経営状況や職員の処遇改善の分析を予定しており、動向を注視するとともに、本市でも、訪問を伴う運営指導などを通じて、引き続き経営状況の把握に努めていく。
仙台市では生活保護世帯などへの水道料金の減免制度を設けているが、本市も生活困窮者への減免制度などを設けてはどうか。
(回答)中核市では4市が実施しているが、生活扶助費と重複することや、財源面から廃止している市もあるため、慎重な検討が必要と考えている。
水道水を供給する柏倉増圧ポンプ場は活断層のすぐ近くにあるため、地震発生時の影響が懸念される。また、停電時はポンプが停止し断水となるが、耐震化や発電機能の整備などの防災対策をどのように考えているのか。
(回答)移動式発電機を使用した停電対応訓練を行うなど、長時間の停電にも対応可能な体制を整えているが、現在取り組んでいる大規模事業の進展や財政状況を踏まえながら、施設の更新を計画していく。
児童・生徒の飲用水の安全性確保のため、小・中学校の水道設備の改修計画を策定し、定期的に改修を行うべきではないか。また、コスト削減のため、配水管から直接給水し、受水槽を新設しない方式や、既存の受水槽を長く使用するために飲み水は配水管から直接給水し、受水槽の水は下水などに活用する方式も検討してはどうか。
(回答)近年の改築では、受水槽式給水と直結式給水を併用し、飲用水は直接配水管から給水している。山形市小中学校施設整備方針などの改訂の際に、水道設備の定期的な改修や給水方式を検討していく。
亡くなる際に自身の希望が叶うのか不安を抱いている一人暮らしの高齢者や身寄りのない人に寄り添うため、終活情報を登録する制度を創設してはどうか。
(回答)疾病や親族関係などの状況の変化に応じて考え方が変化した際の対応など、さまざまな課題もあることから、他市の先進事例の効果や課題を把握し、調査研究していく。
安全で地産地消や食糧自給率の向上などへ寄与する国産の脱脂粉乳を、本市の学校給食のパンなどに使用してはどうか。
(回答)安価で安全性も確保されているニュージーランド産を使用しているが、パンの提供事業者などとも協議し、課題を整理しながら検討していく。
【荒井 拓也 議員】一人ひとりが輝く未来志向の山形へ
山形県立図書館では令和6年度から電子書籍サービスが開始されたが、本市での検討状況はどうか。
(回答)県立図書館との役割分担に配慮しながら、7年度からの導入の検討を進めている。学校や自宅でも気軽に本に親しめるように電子書籍サービスを導入し、読書環境の充実を図っていく。
ヤングケアラーの家事・育児などを一定期間サポートするヘルパー派遣事業を早期に実施すべきではないか。
(回答)訪問を伴う家事代行の実施も含めて、本市の状況を踏まえたさらなる支援を検討していく。
保護者の不安軽減や早期治療につなげるため、本市の3歳児健康診査票の問診の項目に吃音を加えてはどうか。
(回答)吃音を含む言葉関連の問診項目を複数設けているが、医療機関と意見交換を行い、保護者にとって分かりやすい表現であるかなどの観点を踏まえて、今後検討していく。
母乳バンクのドナー登録ができる体制の整備に向けて、産婦人科などの医療機関へ周知を働きかけるなど、多くの赤ちゃんを救うための支援を広げてはどうか。
(回答)ドナー登録施設の周知や設置は、国の動向を注視するとともに、県内医療機関と意見交換を行っていく。
現在運用している山形市コミュニティサイクルに、市民から親しまれる愛称をつけてはどうか。
(回答)さらなる啓発や利用拡大につながると考えられるため、先行自治体を参考に検討していく。
商品を持ち帰った後にごみ袋としても利用できるレジ袋を市指定のごみ袋として販売することで、ごみの排出量の削減を図ってはどうか。
(回答)さらなるレジ袋の消費削減に有効であり、プラスチックごみの排出抑制が図られるため、レジ袋として使用できる指定ごみ袋の作成を検討していく。
時代の変化への対応や、財政負担軽減の観点から、西蔵王放牧場に民間活力を導入し、放牧事業以外に新たな事業を展開してはどうか。
(回答)6年度から、庁内関係課で組織する西蔵王放牧場あり方検討会で運営形態の見直しなどを検討していることから、民間活力の導入も併せて検討していく。
近年の夏季の気象状況を踏まえて、馬見ケ崎プールジャバの屋外プールの使用期間を拡大してはどうか。
(回答)夏休み以外の土日祝日の利用が盛況であることから、経営面や人員確保の状況などを踏まえて、使用期間以外の土日祝日にも屋外プールをオープンすることを検討していく。
【仁藤 俊 議員】「最上義光公」を主人公とした大河ドラマを
最上義光を主人公にした大河ドラマの実現に向けてトップセールスを行うとともに、関係団体をつなぐ架け橋となって官民一体で誘致活動を行ってはどうか。
(回答)関係機関や郷土史研究の有識者と連携するとともに、他地域の取り組み状況などを調査し、メディア関係者との調整を図るなど、効果的な誘致活動を行っていく。
食品ロスの削減に向けて、県と協力して「30・10運動」や「もったいない山形協力店」、「mottECO」の取り組みを推進してはどうか。
(回答)県と連携し、外食時の適量注文や食べきりなどの啓発に加えて、もったいない山形協力店の利用を呼びかけていく。
自己責任で食べ残しを持ち帰るための承諾書を市が作成し、飲食店へ持ち帰りの推進を働きかけてはどうか。
(回答)国が令和6年度中に策定する予定の食べ残しの持ち帰りに関するガイドラインの内容を踏まえながら、承諾書の必要性も含めて検討していく。
災害時の女性避難者への配慮の取り組みはどうか。
(回答)各自主防災会への女性参画の啓発や、参画を促す助成金の拡充を検討している。また、7年度に避難所・避難場所環境整備計画を策定予定であり、女性目線の配慮事項の拡充を検討していく。
災害時のトイレ確保に向けた検討状況はどうか。
(回答)市避難所で災害用携帯トイレを備蓄しているほか、マンホールトイレの拡充に努めており、快適な利用環境の確保に向けて検討していく。
災害時の支援物資の仕分けは、どのように行うのか。
(回答)協定締結先からの物資に加えて、国などからのプッシュ型支援も活用予定であり、山形国際交流プラザに集約後、輸送事業者などが市避難所に配送することとしている。
市保健所のシンクタンクの調査研究項目に「発酵食品の推進」を追加してはどうか。
発酵食品の有効性など、健康寿命の延伸に寄与するさまざまなテーマで調査分析していく。また、山形大学医学部が実施している山形県コホート研究での調査などの取り組みとの連携も推進していく。
発酵食品を使った献立を取り入れる発酵給食の日を設けて、発酵文化などを児童・生徒などへ伝えてはどうか。
発酵食品を多く取り入れた特別献立の実施を検討し、実施に併せて本市の発酵文化などを伝えていく。
孤独や孤立で困っている人の支援のため、つながりよりそいチャットをさらに周知してはどうか。
さまざまな媒体で周知しており、今後もSNSなどを活用して周知していく。
【高橋 公夫 議員】市立商業高等学校入学試験での合理的配慮を!!
フリースクール認証制度を創設し、小・中学生の校外での居場所づくりに取り組む市内のフリースクールへ運営経費の補助などの支援を行ってはどうか。
(回答)フリースクールの運営に取り組む団体を把握し、各団体の意向を踏まえた効果的な支援を検討していく。
送迎が必要な障がい者など、投票所に出向くことが困難な人の投票機会を確保するため、オンデマンド型移動期日前投票所を導入してはどうか。
(回答)茨城県つくば市の実証実験の取り組みを注視しながら、効果や課題を検証していく。
障がいのある生徒への合理的配慮として、入学試験でのタブレット端末の利用を推進するという国の例示もあるが、本市の対応状況はどうか。
(回答)決してタブレット端末を使用させないということではなく、個別の相談に応じて、県教育委員会と協議しながら対応を検討する。
国が合理的配慮として例示する別室受験や試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能やICT機器の活用、口答試験での評価などを本市では行わないのか。
(回答)市立商業高等学校の受験者から要望があった場合には、内容を考慮して検討する。
放課後児童クラブでも家庭と同様にタブレット端末を使用した学習ができるようにWi-Fi環境を整備すべきではないか。
(回答)国へ補助制度の創設や拡充を要望するとともに、他市の事例を調査し検討していく。
発達障がい児などが増加しているため、放課後児童クラブの職員がいつでも臨床心理士などからアドバイスを受けることができる体制や、ストレスに対する心のケア窓口の設置が必要ではないか。
(回答)研修会の開催や、県立こども医療療育センターが専門職員を派遣する事業を行っているが、支援回数の増加などを検討していく。また、市児童健全育成クラブ連絡会と協議し、職員のストレス状況などの実態把握を行う。
全国規模の大会の開催や小・中学校の水泳授業での活用に向けて、バリアフリー機能を備えた屋内50メートルプールを整備してはどうか。
(回答)山形県全体の競技力向上につながる広域的な施設であることから、引き続き県に検討を働きかけていく。
みはらしの丘から通学する第九中学校の生徒が冬期間に安全に通学するため、スクールバスを運行してはどうか。
(回答)管理体制の確保の課題もあることから、引き続き生徒冬季通学費補助金を支給するとともに、バス事業者と現在運行中の路線バスの増便などを協議するなど、通学移動環境の改善を検討していく。
【浅野 弥史 議員】新しい済生館の機能充実を
済生館では小児入院患者の付添者の負担軽減のため、以前から要望のあった付添者からの弁当注文受け付けを令和6年度に開始し、感謝の声が寄せられているが、さらなる負担軽減のため、小児病棟へ保育士を増員してはどうか。
(回答)看護補助者の増員に向けて準備を進めているが、保育士の増員は入院患者の状況なども踏まえて検討していく。
新病院移行と併せて無痛・和痛分娩を導入してはどうか。
(回答)対応する医療スタッフの確保や安全面を考慮しながら検討していく。
食材費が高騰しているため、幼稚園や民間立保育所などの給食費への補助を増額してはどうか。
(回答)国の動向を注視するとともに、財政措置などの必要な支援を行うように国へ要望していく。
幼稚園や保育園では、発達障がいの特性が見られるが診断基準には満たないグレーゾーンの子どもとの関わり方が難しい状況にある。きめ細やかな保育の提供のために、保育士を加配した際などへの支援を行うべきではないか。
(回答)課題と捉えているため、他自治体の取り組み状況などを調査するとともに、障がい児保育受入促進事業の内容の見直しなども検討していく。
部活動の地域移行に向けた今後のスケジュールはどうか。
(回答)モデル事業を継続・拡充しながら、具体的な取り組みや方法を周知する(仮称)山形市部活動地域移行・地域連携推進計画の7年度中の策定を目指している。8年度以降は、環境の整ったところから休日の中学校部活動の地域移行・地域連携を段階的に進める想定となっている。
平日の部活動は任意加入制となるのか。
(回答)8年度以降は、全校で任意加入制となる予定である。
休日のクラブ活動は、小学校のスポーツ少年団と同様の活動となるのか。
(回答)スポーツ少年団と同様に学校が関わらない活動となる。
サル捕獲用大型檻に使用するエサの確保のため、市場などで不要になった野菜などを定期的に譲り受ける仕組みを構築してはどうか。
(回答)農協などと協議しながら仕組みを作っていく。
第十中学校の通学路である市道南館黒沢線の二ツ橋は交通量が非常に多いため、安全対策が必要ではないか。
(回答)歩行者の安全性向上や車両のスピード抑制を図るため、歩行空間と車道を分離するラバーポールを設置するとともに、山形警察署とグリーンベルトの拡幅塗装の協議を行う。
【松田 孝男 議員】地域の絆をつなぐ公共交通サービス向上への新たな展望
ベニちゃんバス無料デーの実施効果と今後の事業展開はどうか。
(回答)令和6年度と5年度の街なか賑わいフェスティバルを比較すると、6年度の乗車人数が約1・9倍に増加したことから、効果的な取り組みと捉えており、他のイベントへの拡大などを検討していく。
南くるりんの本格運行に向けた見通しはどうか。
(回答)運行実験終了後に利用状況やアンケート結果などを詳細に分析してさらなる改善に取り組み、本格運行へつなげていきたい。
税収の増加を図るため、旅先納税の取り組みを拡大してはどうか。
(回答)飲食店や宿泊事業者などと協議しながら検討していく。
蔵王温泉では樹氷鑑賞目的のインバウンド客が急増しているが、蔵王ロープウェイの待ち時間の解消に向けた取り組みはどうか。
(回答)事前予約システムや変動価格制での適正な需要管理、ゲレンデのWi-Fi環境の整備などで待ち時間を緩和するなど、オーバーツーリズムを解消するための事業を実施していく。
子宮頸がんワクチンの定期接種の対象者に個別勧奨を行っているが、対象期間が終了する高校1年相当の未接種者へ再勧奨を行うなど、確実な接種を促進するための取り組みを行ってはどうか。
(回答)引き続き定期接種の未完了者に個別勧奨を行うとともに、SNSの活用など、効果的な方策を検討していく。
COPD対策を第3次山形市健康づくり計画の中に位置付け、理解促進と予防対策の強化を図ってはどうか。
(回答)禁煙や受動喫煙防止につながる施策を計画に盛り込み、市民の理解促進と予防対策の強化を図っていく。
妊産婦の病気やけがの医療費を助成する制度の導入が全国で進んでいるため、本市でも導入してはどうか。
(回答)国の動向を注視しながら調査研究していく。
本市では、第2子以降の育児休業中の放課後児童クラブの利用が認められていないが、子育て世帯の大きな負担となっているため、見直しを行うべきではないか。
(回答)長期休業期間中の保護者の負担や利用児童の環境の変化に留意することも必要と認識しているため、他自治体の状況などを調査研究していく。
全国で導入が進む市営住宅の共益費の行政徴収制度を本市でも導入してはどうか。
(回答)自治会役員の担い手不足などの問題が発生しているため、行政としてどのような対応ができるのか、他自治体の状況などを調査研究していく。
【鈴木 進 議員】安心安全なまちづくりの推進へ!
高齢化などで広報やまがたの配布の負担が大きくなっているため、発行回数を月1回に変更してはどうか。
(回答)SNSなどでの発信が一定程度定着したこともあり、今後の在り方を検討している。
自治活動の推進や広聴・広報活動など、役割の多い自治推進委員の新任者への研修や、他の自治会の事例などを意見交換しながら学べるグループ研修を行ってはどうか。
(回答)自治推進委員長連絡協議会の意見を聞きながら、研修の手法を検討していく。
令和6年能登半島地震の避難者数は輪島市で想定の12倍となり、備蓄食料に不足が生じたが、本市の各避難所での備蓄品の想定はどうか。
(回答)大規模災害時には、国のプッシュ型の支援などを活用する予定だが、発災直後の物資不足や、温かく栄養バランスが取れた食事の提供などの課題が指摘されているため、令和7年度に避難所・避難場所環境整備計画を策定する予定であり、備蓄品の品目や適正数の見直しを検討していく。
大規模災害の発生時に、学校の体育館以外の教室などを避難スペースとして開放することはあるのか。
(回答)避難所・避難場所環境整備計画の策定に併せて、教室などの活用の可能性を関係機関と協議していく。
山形市避難行動支援制度の核となる個別避難計画の作成には、避難行動要支援者本人の同意を得ることなどの課題があるため、まずは支援を必要とする人の把握に取り組んではどうか。
(回答)個別避難計画の策定が7年度から本格化することから、実態把握が困難な人へのアプローチ方法を地域の関係者と協議していく。
「山形市は地震が少ない」という意識が根強く、備えが十分ではないため、新たな地震ハザードマップを作成し、全戸配布してはどうか。
(回答)全戸配布に向けて準備を進めるとともに、住宅の耐震化の促進や地震発生時の安全な避難方法などの啓発に努めていく。
高齢者移動支援サービス検討事業の実施地区を拡大し、認知症カフェへの送迎支援を行ってはどうか。
(回答)モデル事業の成果を踏まえて、地域のニーズに合わせた移動支援の取り組みを他の地域にも展開していく。
市の北部地域を循環する北くるりんの運行に向けた取り組み状況はどうか。
(回答)6年度中に地域の実情とニーズを把握するためのアンケート調査を実施する予定であり、7年度には、先行する南くるりんの検証結果などを活用してコース設定などの具体的な検討を進め、できるだけ早い実現を目指していく。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-642-8404 ファクス番号:023-641-9160
giji@city.yamagata-yamagata.lg.jp