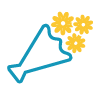一般質問(令和6年6月定例会)
令和6年6月定例会で行われた一般質問は、以下のとおりです。
(ここに掲載した一般質問は、市議会報229号に掲載したものを再掲載しており、質問内容は実際の質問を要約・抜粋したものです。)
【中野 信吾 議員】山形市と仙台市を直接結ぶ高規格道路の整備を!
中核市の本市と政令指定都市の仙台市を直線的に結ぶ高規格道路が必要ではないか。
(回答)中枢中核都市同士の結びつきを強め、地域経済の連携での地域振興の促進や災害時の緊急輸送路の確保を図る観点からも、国道48号や国道286号の代替となる路線での機能強化が重要であると認識しており、国土交通省東北地方整備局へ要望を行っている。
自走式のトイレカーを導入し、導入済みの自治体との間で、災害時にトイレカーを相互派遣する協定を締結してはどうか。
(回答)仙台市など109自治体と災害時応援協定を締結しており、災害時のトイレ対策全般を検討する中で、提案の内容も研究していく。
令和5年度に事業着手した(仮称)山寺防災1号線の進展状況はどうか。
(回答)県や山形警察署と主要地方道山形山寺線との交差位置の協議を行っており、協議結果を踏まえて、概略設計や路線測量を行い、地元への説明会を開催する予定である。
山形北インター産業団地の造成などで楯山駅の利用者の増加が見込まれるが、交通系ICカードの導入に向けたJR東日本との協議の状況はどうか。
(回答)JR東日本本社に出向き、楯山駅をはじめとする市内の交通系ICカード未対応駅への導入の必要性を説明しており、引き続き働きかけていく。
十文字西踏切の拡幅改良を早急に行うとともに、楯山駅の北口改札と南北自由通路も整備してはどうか。
(回答)十文字西踏切は、歩道整備と車道拡幅での改良を検討しており、国の指針に基づき、十文字東踏切の廃止や南北自由通路と北口改札の整備などと一体的に検討を進めることとしている。
公共交通部門ではタクシーを活用した実証実験を行っているため、高齢者外出支援事業でもタクシーなどの利用を支援対象としてはどうか。
(回答)市全体の公共交通ネットワーク化を目指してモデル事業を実施しており、今後、全市的な公共交通の再編を目指す中で、バス以外の公共交通機関を含めた支援の在り方などを検討していく。
山形北インター産業団地の第二期整備区域の整備計画を早期に策定し、第一期整備区域の完売後も、市内に産業用地がない空白期間が生じないようにすべきではないか。
(回答)産業用地の確保は全国的な課題であり、地域未来投資促進法の整備などの動きを的確に捉えた開発手法を検討している。また、空白期間が生じないように取り組む必要があると捉えており、第二期整備区域の整備では、スピード感を持って取り組んでいく。
【安久津 優 議員】山形駅周辺の活性化を!
コロナ禍後はタクシー待ちの列も見受けられることから、利便性向上のため、山形駅東口タクシー乗り場付近にベンチを設置してはどうか。
(回答)市民や観光客などの利便性向上につながるため、関係者と意見交換しながら、検討していく。
日本一の観光案内所の整備が構想どおりに進むのであれば、建設される新たな建物の2階に入口を設けた上で、ペデストリアンデッキを拡張してつなげてはどうか。
(回答)旧ビブレ跡地に民間ビルが建設されることを想定し、ペデストリアンデッキをビルの2階部分に接続する方向で検討を進めている。
災害時の通信環境の確保のため、公民館やコミュニティセンターのすべての部屋でWi-Fiがつながるように整備を進めてはどうか。
(回答)携帯電話事業者などと連携しながら、Wi-Fi環境の拡大など、災害時の通信確保に向けた整備を進めていく。
効率的な自治会運営を支援するため、アプリを活用した電子回覧板の全世帯普及に向けて取り組んではどうか。
(回答)先行事例を注視するとともに、より便利な回覧の方法を町内会・自治会などと意見交換していく。
卒業生がいつでも懐かしむことができるように、小学校などの旧校舎を解体する前に、外観と校内を撮影して市ホームページなどで公開することとし、まずは、西山形小学校の旧校舎で実施してはどうか。
(回答)同窓会などの地域の関係者が旧校舎の画像などのデジタル保存を希望する場合には、その方法などの協議を行いながらサポートしていく。
市民会館をはじめとする市民が思い出深く感じる施設は数多く存在しているが、建物の記録はどのように行っていくのか。
(回答)旧市民会館という位置付けになった際に、どのように思い出として残していくかなども含めて検討していく。
きれいでおいしい水道水の提供のための工夫はどうか。また、おいしさを市民が誇れるようにPRすべきではないか。
(回答)水源涵養林を整備し、水質浄化と良質な水源の確保に努めている。また、活性炭での高度浄水処理を行い、きれいでおいしい水道水の供給に努めており、施設見学や出前講座などでPRしていく。
文化活動に取り組む市民から依頼があれば市立商業高等学校の部活動として取り組むなど、文化活動の振興や技術継承を図ってはどうか。
(回答)若者が世代間交流を通じて文化芸術活動を気軽に体験できる機会を創出することなどが重要であり、文化芸術団体と連携して課題を共有しながら、振興に努めていく。
【鈴木善太郎 議員】老朽化が進む第十小学校、教育施設の格差解消を!
東沢地区には豊かな自然と名所旧跡が多く存在するため、薬草湯入浴などもできる健康ツーリズムの拠点づくりに取り組んではどうか。
(回答)東沢地区が主体となり、地域資源を観光・レクリエーションの場とするプロジェクト会議を立ち上げる予定であることから、地域と意見交換を行いながら、拠点づくりの可能性を探っていく。
旧大沼の跡地利用や済生館の改築、市民会館の新築移転などの大型プロジェクトが予定されているが、健全財政の維持に向けた考えはどうか。
(回答)将来負担比率などは一定程度上昇すると想定されるが、事業計画の年度間調整に取り組むとともに、積極的に国庫補助金などを活用し、健全財政の維持に努めていく。
第十小学校校舎は整備から60年が経過し、老朽化が進んでいる。教育施設の格差解消は最優先に取り組むべき課題と考えるがどうか。
(回答)築50年以上の学校が10校以上あるため、山形市小中学校等施設整備方針などの改訂を令和6年度に進める中で、方向性を検討していく。特に建築年度が古い学校は、劣化度や事業費などの効率性を精査し、リノベーションや改築などの整備手法の調査を行うことを検討している。
道路事情の良くない住宅密集地区での空き家の増加が見られることから、市域全体の居住環境の整備を促進すべきではないか。
(回答)狭い道路の改善や空き家の増加防止など、住宅密集地区での災害防止に向けて、地域と連携した空き家対策のモデル事業を城西や鈴川地内で実施しているが、他自治体の事例などを調査研究していく。
一般国道112号山形南道路は、東西の分離を招く可能性がある盛土構造での整備が示されているため、平面交差での整備を要望してはどうか。
(回答)接続する道路や周辺の土地利用などさまざまな観点からの検討が必要であるため、地域の発展につながるように、引き続き国へ要望していく。
特別養護老人ホームは物価高騰などで経営が圧迫され、介護職員の確保が困難になるなど、厳しい環境に置かれているため、助成などを行うべきではないか。
(回答)食費への財政支援などを行うように、6年度も国へ要望している。また、人材確保に向けて、事業者が処遇改善加算を取得できるように周知を徹底するとともに、指導・助言などを丁寧に行っていく。
幕末の水野藩政時代の歴史的資料の散逸を防ぐため、「水野藩歴史資料館」を東大手門櫓へ設置してはどうか。
(回答)資料の所有者などと協議しながら保存のための措置を検討するとともに、水野家由来の資料は、特別企画展などでの展示を検討していく。
【斉藤 栄治 議員】福祉と医療の充実と健康都市を推進せよ!
持続可能な地域包括ケアシステムの構築を目標とする山形版※地域医療連携推進法人の設立を関係機関に働きかけてはどうか。
(回答)関係機関と連携を図りながら各種施策を進めており、本市の実情に応じた地域包括ケアシステムの確立に向けた取り組みを、引き続き推進していく。
県と同様にがん治療者の相談を広く受け入れるためのサポート窓口を設置し、県との連携を図ってはどうか。
(回答)各相談窓口の周知と各相談支援センターとの連携を図り、より気軽で親切な相談体制となるように、既存のケア体制の利用拡大などに取り組んでいく。
山形市休日夜間診療所で市薬剤師会が実施している医薬品相談事業への補助金が、実態に合った額となっているか調査を行った上で、増額を検討してはどうか。
(回答)実態を詳細に伺いながら、必要な支援を検討していく。
健康ポイント事業SUKSKの啓発活動として、市内調剤薬局との協力体制を構築してはどうか。
(回答)市薬剤師会と協議しながら具体的に検討していく。
開催地が大都市圏に固定されない国民スポーツ大会は、地方都市の子どもたちの目標となり、地域経済の活性化などにもつながるため、継続すべきであると考えるがどうか。
(回答)スポーツの振興と文化の発展、地域経済の活性化に寄与する価値のある大会であるため、継続していくことが望ましいと考えている。
山形花笠まつりのパレードを、道幅の広いすずらん通りや栄町通りで行ってはどうか。また、パレード開始を待つ人に楽しんでもらうため、出店を早めることを商店街などへ働きかけてはどうか。
(回答)パレードコースは、中心市街地の開発などの状況の変化を見据えて調査研究していく。パレード開始前から楽しんでもらうための取り組みは、山形県花笠協議会などと検討していく。
都市計画道路四日町山家町線の馬見ヶ崎橋から国道13号までの区間の早期着工が望まれるが、進展状況はどうか。
(回答)令和6年度に道路設計、7年度から用地測量を行い、一部区間の事業認可の取得を目指すが、残地発生などの課題があることから、解決に向けた話し合いを行い、早期完成に向けて事業を進めていく。
県と本市が7年度までの完成を目指している鈴川第2号幹線の進展状況はどうか。
(回答)県の野呂川の河川改修が時間を要しているため、改修促進を働きかけていく。国道13号区間は、詳細設計が完了し、国道管理者などと工事実施に向けた協議を進めており、今後も関係機関と連携し、早期完成を目指していく。
【菊地健太郎 議員】国力低下に地方として歯止めを!
日本は人口減少社会に突入し、国力が低下しているが、一地方自治体として本市はどのように国力低下に歯止めをかけていくのか。
(回答)活力ある持続可能なまちであり続けるため、山形北インター産業団地への誘致促進などの産業施策や観光施策を進めるほか、出産・子育て支援などの安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりの充実を図っていく。
中心市街地のにぎわい創出のため、新たなプラネタリウムを整備する際は、少年自然の家ではなく、中心市街地へ設置してはどうか。
(回答)少年自然の家に残す機能や導入する機能などの整理を行うため、基本計画策定に向けた事業者の公募を行っており、総合的に検討していく。
街なか観光でも温泉を楽しめるように、整備予定の日本一の観光案内所周辺に温泉施設を整備してはどうか。
(回答)中心市街地に望まれる機能の一つと認識しており、調査研究していく。
旧大沼の解体までの間の有効活用策として、建物を撮影会やサバイバルゲームなどの利用へ貸し出してはどうか。
(回答)閉店後さらに老朽化が進み、建物内部の利用は危険が伴う状況であるため、外の壁面やセットバック部分などのさらなる活用に努めていく。
廃業や企業の合併・買収などで県外企業の傘下に入る企業が増えていることから、地方らしさを持続させるために、事業承継支援に取り組んではどうか。
(回答)関係機関と意見交換しながら、さらなる支援の在り方を調査研究していく。
タイからのインバウンドはコロナ禍前よりも増加している。固定の山形ファンをつくるため、スポーツ・文化交流を盛んにしてはどうか。
(回答)山形の魅力をタイの人に伝える有効な手段であることから、関係団体などと協議しながら、今後の方向性を検討していく。
人手不足の介護施設では外国人介護人材を受け入れているが、人材が定着しないため、県では令和6年度から支援を拡充している。本市でも支援に取り組んではどうか。
(回答)県や関係機関と連携し、県の支援制度の一層の周知を図っていく。また、本市が独自に設置した山形市介護人材確保推進協議会で有効な取り組みを検討していく。
山形市屋外広告物条例に抵触することから、市内商店街が「ほこみち」推進のための事業を実施できない状況となっている。早期に条例を改正してはどうか。
(回答)今後、景観審議会などの意見を聴き、できるだけ早期に条例改正を提案したいと考えている。
【中川 智子 議員】誰一人取り残されない学びの保障を
不登校の児童・生徒の居場所づくりは重要であることから、誰一人取り残されない学びのための取り組みに力を入れるべきではないか。
(回答)適応教室「風」の設置や、学校内の居場所づくりなど、不登校の未然防止に向けた手立てを講じており、今後も誰一人取り残されない学びの保障の実現に努めていく。
AEDは電極パッドを肌に貼って使用することから、女性への使用をためらう場合があるため、使用方法のリーフレットや胸部を覆うことができる三角巾などを設置してはどうか。
(回答)電極パッドは、衣服などを少しずらすことで、肌の露出にも配慮しながら迅速に貼ることが可能であるため、適切な使用方法のさらなる普及啓発を図っていく。
聴こえに不安を感じている人への支援として、介護保険課に設置している軟骨伝導イヤホンをほかの窓口にも設置してはどうか。
(回答)軟骨伝導イヤホンは、大きな声で話さず円滑にコミュニケーションがとれ、プライバシーの保護にもつながるため、個人情報を取り扱う窓口を中心に設置を進めていく。
子宮頸がん予防ワクチンの安全性などを正しく理解した上で接種の判断ができるような個別通知を送付してはどうか。また、キャッチアップ接種対象者で未接種の人には、初回接種期限までの間に、再度通知を行ってはどうか。
(回答)有効性や安全性を伝えられるように、勧奨内容のレイアウトの工夫や二次元コード配置などを行う。勧奨の時期や回数は、より効果的な方策を検討し、実施していく。
本人の胃がんや将来の母子感染を防ぐため、中学2年生を対象としたピロリ菌抗体検査を実施してはどうか。
(回答)医療機関の意見や他市の状況などを踏まえて、必要性や有効性を調査研究していく。
プレコンセプションケアの普及啓発にどのように取り組むのか。また、男女ともに利用しやすい窓口となるように啓発方法を工夫し、相談体制の充実を図ってはどうか。
(回答)女性の健康相談は随時受け付けている。今後は女性に限らず気軽に相談できることを周知するとともに、若年世代に向けた普及啓発を行い、利用しやすい窓口となるように工夫していく。
水道直結型で常温と冷水を選べるマイボトル専用の給水スポットを市有施設に設置し、プラスチックごみの削減や熱中症予防に向けた取り組みを推進してはどうか。
(回答)マイボトル持参率の向上のため、さらなる周知啓発を行っていく。また、市有施設利用者のニーズに応じて、設置の必要性を検討していく。
【髙橋 康輔 議員】「減塩」をさらに進めていきいき健康に
人口減少や出生率低下の課題の解消には、男女が平等に家事育児を行う環境整備などが重要であるが、地域の実情も踏まえてどのように取り組んでいくのか。
(回答)男性の育児休業取得は、ジェンダーギャップの解消につながるため、引き続き取り組んでいく。また、若年女性の地元定着や地元企業内での女性活躍の可能性拡大の取り組みも進めていく。
本市の推定食塩摂取量は、男女ともに国や県の目標値を上回っている。覚えやすい言葉で意識や行動を変える取り組みが必要ではないか。
(回答)減塩講座の実施方法の見直しや減塩レシピなどの周知、SUKSK給食の実施に取り組んでいくとともに、ネーミングを含めて減塩施策の在り方を検討していく。
ソフト麺の製造が終了して学校給食から姿を消したが、適正な塩分量として計算されたソフト麺用のスープなどのレシピを一般家庭向けに公開してはどうか。
(回答)市民の減塩活動の推進に役立つと考えるため、ホームページなどでの公開に向けて作業を進めていく。
千葉県いすみ市では、減塩協力店で薄味を希望することができる。また、穴付きのレンゲに替えた場合でも味や満腹感は変わらないという研究結果があるが、今後どのように減塩に取り組んでいくのか。
(回答)健康寿命延伸のためには自覚することが大切であるが、若い世代ほど意識が低いため、市民の意識向上に向けて積極的に取り組んでいく。
「ラーメンの聖地、山形市」をアピールするモニュメントの設置など、撮影スポットを整備することで、観光資源として活用してはどうか。
(回答)観光需要の掘り起こしにはSNSなどでの情報発信と拡散が大きな役割を果たしており、SNS映えするスポットの選定など、調査・検討を進めていく。
男女共同参画の視点を地域防災計画の総則に位置付けるべきではないか。
(回答)女性目線での災害対応が重要と考えており、総則への位置付けも検討していく。
市避難所や地区避難所へWi-Fi環境を整備してはどうか。
(回答)市避難所の災害時の通信確保に向けた整備を進めるとともに、自主防災組織への補助の見直しも検討していく。
自由に意見を表明でき、将来のキャリアを描きながら働ける環境が、よりよい行政施策実施につながると考えるが、今後どのように市職員の人材育成を行っていくのか。
(回答)職員が具体的にキャリアプランを描くことができる研修の在り方を検討していく。
【斎藤 淳一 議員】水道料金の見直しを
県体育館・武道館の整備に向けて、整備の在り方や方法を県と十分に協議すべきだと考えるがどうか。
(回答)霞城公園整備の進展状況を踏まえて、現施設の撤去の時期や施設の在り方の課題を県と共有し、協議していく。
本市の歴史や風土に関心を持ってもらえるように、東大手門櫓やぐら内の展示物を工夫してはどうか。また、空調設備を設置してはどうか。
(回答)展示内容などの見直しを検討しており、令和6年7月末をめどにリニューアルする予定である。空調設備は、移動式の簡易エアコンの設置に向けた調査を行っていく。
家庭的保育事業の保育の質の向上と補助者の安定雇用のため、入所者が2人以下の場合にも補助者を雇用できるように支援してはどうか。
(回答)国の動きや他自治体の状況を確認しながら、2人以下の利用の際の補助制度を調査研究していく。
市産材の利用拡大に向けて、関係各課の連携をさらに強化してはどうか。
(回答)市産材利用拡大推進連絡会議で利用状況の検証を行うほか、山形市産材利用拡大連携協定の締結団体から施工手法などの情報提供を受けて、利用拡大に努めていく。
令和13年度に見崎浄水場の廃止が予定されており、県営村山広域水道に切り替えることで浄水単価が下がると考えられるが、水道料金を見直す余地はあるのか。
(回答)料金収入の減少は今後も続く見込みであり、水道施設の統廃合に伴う整備費の見通しも立たないため、すぐに料金を下げることは難しいと考えている。
能登半島地震での断水などの状況から、災害対策マニュアルを根本的に見直す必要があると考えるがどうか。
(回答)被災地での応急活動の経験を踏まえて、災害対策マニュアルの見直しを行っており、援助を受け入れる側の受援マニュアルの整備にも取り組んでいる。
大災害発生時にボランティアなどを受け入れるための指針が必要ではないか。
(回答)大規模な災害が発生した際は、山形市社会福祉協議会に災害時ボランティアセンターの設置を要請し、運営に必要な支援を行う。また、国などからの応援を円滑に受け入れるための受援計画を策定する予定である。
コミュニティサイクルのサイクルポートに、電動アシスト自転車の劣化を防ぐための屋根を設置してはどうか。
(回答)これまでの利用状況の検証などを行い、より利用が期待できる場所へのサイクルポートの再設置を検討しており、できるだけ屋根のある場所へ設置するなどの工夫をしていく。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-642-8404 ファクス番号:023-641-9160
giji@city.yamagata-yamagata.lg.jp