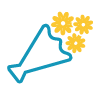一般質問(令和7年6月定例会)
令和7年6月定例会で行われた一般質問は、以下のとおりです。
(ここに掲載した一般質問は、市議会報233号に掲載したものを再掲載しており、質問内容は実際の質問を要約・抜粋したものです。)
【遠藤 吉久 議員】市職員採用試験に 「難病患者枠」の創設を!!
寛容で弱者に寄り添う地域共生社会の実現に向けて、山梨県の事例を参考に、市職員の採用試験に難病患者枠を創設してはどうか。
(回答)現在も、難病患者も含めて広く募集しているが、受け入れ態勢や勤務形態、職務内容などの整理すべき点もあることから、他自治体の先行事例を調査研究していく。
災害時の透析患者や透析施設への支援をどのように考えているのか。
(回答)庄内・最上地域を中心に発生した豪雨災害では、道路の浸水で透析施設までの移動が困難となった事例も発生したことから、県や関係団体などと連携し、透析施設への移動を確保することで円滑に透析治療を受けられるように支援していく。
総合スポーツセンターの周辺に、新体育施設と多機能屋内スケート場を整備してはどうか。
(回答)公共交通機関などの交通アクセスの利便性が高い中心市街地が望ましいと考えているが、今後の県との話し合いの中でさまざまな要素を考慮しながら決定していく。
総合スポーツセンター屋外スケート場は老朽化しているが、今後の在り方をどのように考えているのか。
(回答)県が屋内スケート施設の整備を検討することとなったため、その施設概要や利用状況などを検証した上で、今後の在り方を再検討していく。
重要事業要望として千歳橋の4車線化を県に要望しているが、県は引き続きフリーレーンの社会実験を継続することとしており、一時しのぎの対応と思える。都市計画を進める上で4車線化をどのように考えているのか。
(回答)フリーレーンは、4車線化に至るまでの当面の取り組みであり、抜本的な解決には至っていないと認識している。都市計画道路美畑天童線は山形市北部地区と中心市街地を結ぶ都心直結道路として重要な幹線道路であることから、今後も重要事業として4車線化を県に要望していく。
これまでの農業施策は、価格転嫁の観点が十分に議論されないまま展開されてきた。物価高騰の影響を価格へ反映させることが難しい状況だが、農業をなりわいとするための価格転嫁を、どのように考えているのか。
(回答)農業者が持続的な農業経営を行っていくためには、生産コストに見合った農業所得の確保が必要であり、国では、令和7年6月の通常国会で、農畜産物の適正な価格形成に向けた法案を可決させ、8年4月の全面施行に向けて詳細を詰めていくこととしている。今後、国が指定する品目ごとのコスト指標の作成や農畜産物の適正な価格形成の動向を注視し、山形市農業戦略本部で必要な施策を検討していく。
【高野 英昭 議員】地域の強みを活かし、賑わいの創出を図れ!
国は水田活用の直接支払交付金の5年水張りルールの見直しを示したが、今後どのように対応していくのか。
(回答)令和9年度に策定予定の第7次山形市農業振興基本計画に国の見直しを反映し、持続可能な農業の実現に向けて取り組んでいく。
県や近隣市町と連携し、須川西部地域にジビエ加工センターを設置してはどうか。
(回答)県や近隣市町と意見を交換しながら、広域連携での施設運営や観光資源としての有効活用策を調査研究していく。
鳥獣被害対策実施隊設立10周年を記念して狩猟フェスタを開催し、狩猟者の顕彰と活動の広報を行うことで、人材の育成につなげてはどうか。
(回答)狩猟者の功績を顕彰しパネルの展示やイベントの開催を行うとともに、人材確保のための取り組みを行っていく。
双葉地区の活性化のため、農村RMOの組織化を支援してはどうか。
(回答)県や関係機関と連携し、引き続きFUTABAテラスへの伴走支援を行っていく。
紅花などの地域食材を活用したフレンチなどのレストランを、旧双葉小学校で週替わりに開店できるようにしてはどうか。
(回答)他地域の事例を調査し、検討していく。
中山間地域に居住する高齢者への雪下ろしなどの支援制度を拡充してはどうか。
(回答)積雪量や地域の状況を踏まえた制度を検討していく。
きつね一巡りサイクリングロードに案内表示や休憩所などを整備するとともに、コミュニティサイクルとしてeバイクを配置してはどうか。
(回答)県や山辺町と連携して効果的な整備方法などを検討し、観光客のニーズを把握しながらコミュニティサイクルの配置を検討していく。
円仁を支えた張保皇(チャンボコ)の出身地である韓国莞島(ワンド)と本市の草の根交流を広げてはどうか。
(回答)草の根交流の在り方などを地元と相談していく。
最上義光歴史館は老朽化が進んでいるため、霞城公園内に資料展示館を整備し、収蔵品を展示してはどうか。
(回答)歴史館の機能移転も含めて検討し、最上義光の功績や山形城の歴史を広く知ってもらうことを目指していく。
英語圏であるフィリピンから優秀な人材を招致しALTを10倍に増やすことで、英語教育を充実させてはどうか。
(回答)他自治体の取り組みを参考に調査研究していく。
地域版空き地・空き家バンクの運営費に対する補助制度を創設してはどうか。
(回答)各団体の活動状況を踏まえて検討していく。
【中川 智子 議員】市民の実情に即した支援を
定検診などの検査項目にナトカリ比測定を追加するとともに、カリウムを摂取しやすい調理法を教えるセミナーなどを開催してはどうか。
(回答)令和7年度から、推定食塩摂取量検査の際にナトカリ比の測定も行う予定である。また、ナトカリバランスがテーマのSUKSKレシピコンテストを新たに開催するなど、ナトカリバランスに配慮した食生活の普及啓発に取り組んでいく。
ギャンブル等依存症に苦しむ人や家族が相談できる体制づくりが重要ではないか。
(回答)市保健所での精神保健福祉相談や家族会への紹介などを行っており、当事者や家族が安心して相談できるように、関係機関と連携して相談体制を充実させていく。
重度障がい者などへの通勤支援や職場での支援を行う重度障害者等就労支援特別事業が開始されたが、市民への周知や企業への働きかけをどのように行っていくのか。
(回答)市ホームページへの掲載や障がい福祉サービスを調整する相談支援事業所への説明会を実施しており、円滑な事業の実施と利用拡大に向けて、関係機関と連携しながら周知していく。
視覚障がい者が安心して外出できるように、個室トイレの中など設備の詳細を案内できるナビレンスを市内公共施設に設置するとともに、さらなる普及を図ってはどうか。
(回答)他市の状況やニーズなどを踏まえながら、調査研究していく。
老人福祉センター黒沢いこい荘の現在使用されていない浴場を、高齢者に限らず、疾病などのさまざまな事情のある人が利用できる家族風呂として活用してはどうか。
(回答)使用を再開するためには多くの修繕が必要となることが見込まれるため、関係機関の意見を聞きながら、総合福祉センター障がい者浴室の利用対象者の見直しや民間施設の利活用も含めて調査研究していく。
作業効率化と職員の負担軽減のため、デジタル技術を活用したごみ収集効率化システムを導入してはどうか。
(回答)デジタル技術の活用は、収集事務の効率化などに有効な手段の一つと考えており、導入自治体の状況や効果などを調査研究していく。
物価高騰の影響を受ける市民や事業者への支援に柔軟に活用できる重点支援地方交付金を有効活用し、市民の負担軽減に取り組んではどうか。
(回答)7年度は、食料品価格の物価高騰の影響を考慮して、保育所及び学校給食費負担軽減事業などを当初予算に計上しているが、新たに交付金が追加交付されたため、引き続き本市の実情に合った支援を行っていく。
【小田 賢嗣 議員】やさしい山形、働ける山形、暮らせる山形へ
市内の就労継続支援B型事業所の1人当たり工賃の平均月額が、全国と比較して低くなっているため、生産品の販路拡大や安定的な購入などの支援に取り組んではどうか。
(回答)山形市自立支援協議会で生産性向上や販路拡大などの支援体制を検討しており、働きやすい環境の整備も含めて、工賃向上に取り組んでいく。
市職員の病休予防を強化するとともに、病休者のいる職場には定数外での補充などの柔軟な対応を行うなど、新たな長時間労働を防ぐための取り組みを行ってはどうか。
(回答)医師の面接指導の対象を拡大するとともに、時間外勤務削減のためのヘルプデスクを設置して相談に応じながら、市民サービスの維持向上と業務の効率化の両立に向けて取り組んでいる。引き続き、職場環境の整備に努めていく。
働き方の選択肢を増やし、職場としての魅力向上や職員の能力発揮につなげるため、市役所で選択的週休3日制を導入してはどうか。
(回答)先行自治体を参考にしながら、導入を検討していく。
交通結節点に位置付けられた楯山駅の南北自由通路と北口改札などの整備や、駅周辺の十文字西踏切の拡幅などの進展状況はどうか。
(回答)楯山駅周辺整備の基本計画策定に向けて調査を行うとともに、十文字西踏切が改良すべき踏切道に指定されるように調整を行うなど、早期実現に向けて取り組んでいく。
タクシーの利便性向上のため、日本版ライドシェアの導入を働きかけてはどうか。
(回答)タクシー事業者などの関係団体と意見交換を行いながら、動向を注視していく。
広報やまがたの配布は自治会などが担っているが、高齢化などで将来の負担増が想定されるため、日本郵便のポスティングサービスの活用を検討してはどうか。
(回答)配布と併せて高齢単身世帯への声がけを行うなど、地域コミュニティを維持する活動なども担っているため、現在の配布方法を継続していく。
持続的な物価上昇に伴い現金価値の低下が懸念される中、資産を適切に管理する必要性が高まっている。基礎的な金融知識や判断力を身につける資産運用の講座を開催してはどうか。
(回答)各公民館で幅広い世代を対象とした金融関連講座を開催しており、今後も社会状況を踏まえた講座の実施を検討していく。
卓球やラージボール卓球の多世代交流と健康増進の効果を活かすため、新たに競技施設を建設するなど、環境整備を進めてはどうか。
(回答)民間施設も多数あるため、全体的なバランスを考慮しながら、環境の維持・向上に努めていく。
【石山 廣昭 議員】「持続可能な農業」に向けた施策を拡充せよ!
農畜産物の価格形成関連法が成立したが、早急に具体的な制度設計を示すように国へ要望すべきではないか。
(回答)持続可能な農業と安定した食料供給体制を築く変革の時期であり、生産者が安心して生産できる制度設計を早急に示すように要望していく。
山形市農業戦略本部会議での中山間地域へのスマート農業の技術活用支援に向けた検討状況はどうか。
(回答)令和7年度に農協や農機具メーカーなどとの連携協定の締結を予定しており、RTK固定基地局の利用促進セミナーの開催や、ドローンなどのスマート農業機械の活用を検証していく。
明治地区では流域治水に貢献する田んぼダムに取り組んでいるが、より多くの地区に広がるように、農業関係者へ働きかけてはどうか。
(回答)広域的に取り組むことで、より効果が発揮されるため、実施地区が拡大するように今後も導入を促していく。
鳥獣対策は恒久的な取り組みが必要であることから、農業被害への対策から鳥獣の捕獲・管理・保護までを一元管理する専門部署を早急に設置すべきではないか。
(回答)山形県鳥獣被害防止協議会と連携を図りながら、鳥獣の捕獲と管理・保護を一元管理する他市の体制を調査研究し、検討していく。
上水道未給水区域の市民が安全・安心に暮らしていくため、給水施設の整備や維持管理を市が直接担うなど、将来を見据えた水道の在り方を、どのように考えているのか。
(回答)住民の減少や高齢化、施設の老朽化が想定されるため、今後も水質検査への補助を継続し、未給水区域での施設の更新の在り方を検討していく。
高瀬駅と楯山駅へのSuicaの導入をJR東日本へ働きかけてはどうか。
(回答)引き続きJR東日本に働きかけるとともに、仙山線整備促進同盟会としても、仙山線の利便性向上と利用拡大に向けて働きかけていく。
最上紅花と地元食材を活用した、ふるさと納税の返礼品となる商品の開発や、現地体験型の返礼品を造成することで、紅花生産者の意欲向上や観光振興につなげてはどうか。
(回答)生産者や開発事業者と商品開発などの調査研究を進めていく。
高齢者が地域社会に積極的に参加する機会が増えるように、外出の意欲を高める仕組みを高齢者外出支援事業に取り入れてはどうか。
(回答)外出の促進には外出先や移動手段の周知も重要であるため、魅力的な文化施設や公共交通の利便性などを周知するとともに、適正な受益者負担も含めて調査研究していく。
【安久津 優 議員】時代に合わせてルール改正を!
山形駅東西自由通路の山形市の管理区分は営利目的での使用が制限されているが、日本一の観光案内所の周辺エリアとして活用するため、個人での物販やイベントの開催ができるように許可基準を改正してはどうか。
(回答)他市の取り組みを参考に、山形駅東西自由通路連絡協議会と調整し、早急に許可基準を改正していく。
山形駅のバス乗り場は東口に集中しており、バス待ちの列が通行の妨げとなる場合があるため、観光客の利用が中心の蔵王温泉行きバス乗り場を西口に移転してはどうか。
(回答)日本一の観光案内所の整備と併せ、観光客が快適に移動できる動線を検討していく。
日本一の観光案内所の整備に伴い、ペデストリアンデッキから山形駅東口周辺施設へ向かう導線をどのように考えているのか。
(回答)築50年を経過している建物もあり、再開発の必要性が高まっているエリアと認識していることから、再開発の意向を探りながら延伸や接続の考え方を整理していく。
山形駅東西自由通路の東側出口に、フォトスポットとなる魅力的な看板やモニュメントを設置してはどうか。
(回答)日本一の観光案内所の基本構想の中で、旧ビブレ跡地の機能として重視すべき要素の一つとしており、令和7年度に策定予定の基本計画の中で内容を整理していく。
人口減少や人口構造の変化に伴い取り組むべき施策が変化することを、広報やまがたなどで市民へ周知すべきではないか。
(回答)人口構造の変化から生じる課題に対応していくため、発展計画2030では持続可能なまちづくりに取り組んでいくこととしており、広報やまがたや新聞紙面などで周知を行っている。また、市内全30地区で説明会を開催する予定で、市民へ直接説明する機会を設けるとともに、SNSなどのさまざまな手法で丁寧に説明していく。
安価に整備可能で農地の多目的利用も期待できる田んぼダムの広範囲での整備に向けて、耕作者に協力を要請してはどうか。
(回答)明治地区と柏倉地区で取り組んでもらっており、多面的機能支払交付金を活用した支援や、積極的なPRに努めている。引き続き取り組み拡大に向けて呼び掛けていく。
建築物遮熱・断熱対策事業費補助金の予算を増額し、公平性の確保のために支給方法を抽選に変更してはどうか。
(回答)これまでの申請状況などから事業のニーズや効果を把握した上で予算の増額を検討していく。なお、支給方法を抽選にすると早期の施工が難しくなるため、現時点では先着順が適切と考えている。
【斎藤 淳一 議員】市南部のランドマークとなる新駅の整備を!
市南部への新駅整備に向けたJR東日本との協議状況はどうか。また、新駅の主な利用者はどのように想定しているのか。
(回答)令和3年から協議を進めており、令和6年度は駅施設や駅前広場の配置など、必要な機能の調査と整備内容の検討を行った。また、乗り換え機能として南くるりんやコミュニティサイクルなどの二次交通を整備する予定で、奥羽本線沿線の住民に加え、市南部の市民が中心市街地へ通勤や通学、通院する際などに利用することを想定している。
闇バイトに関連する強盗や空き巣などが多発し、市民の防犯意識が高まっていることから、自治会などが防犯カメラを設置する際の補助制度を創設してはどうか。
(回答)社会情勢の変化に合わせた防犯体制の強化は重要であり、他自治体の取り組みを踏まえて調査検討するとともに、地区の要望も調査していく。
宿泊税導入に向けた関係者との協議状況はどうか。
(回答)さまざまな意見が出されているが、制度の概要や導入の意図はおおむね理解してもらったと感じている。今後は、外部有識者を含めた検討委員会を設置し、制度の概要をさらに固めていく。
宿泊税の税額や使途、罰則規定の考え方はどうか。また、県との協議状況はどうか。
(回答)現在は、市単独で宿泊税の検討を行っており、税負担の公平性や徴収する際の長所と短所なども踏まえて税額を検討していく。また、税の使途として、特定のエリアへの配分ではなく、観光コンテンツを磨き上げることで市内全体の宿泊者数が増えれば、税収も宿泊事業者の収益も上がることを意識して活用していく。なお、罰則は、ほかの申告納付が必要な市税と同様であり、不申告や虚偽申告となった場合は、地方税法の定めに基づくこととなる。
日本一の観光案内所を実現させるため、来訪者が最大限満足できるサービスを提供する「日本一の観光案内人」の育成と配置が必要ではないか。
(回答)人材の育成と配置は重視すべき要素と認識しており、「暮らしと観光がつながる」というコンセプトを具現化するため、基本計画を策定する中で整理していく。
市産材べにうっどのブランド化と利活用促進のため、市が発注する建築物の仕様書やPFIなどの要求水準書へべにうっどの使用を明記すべきではないか。
(回答)大規模な市有施設の整備には、べにうっどの活用を推進しており、今後も積極的に活用していく予定である。市有施設に率先して使用し、市民や事業者などから良さを知ってもらうことで、民間での利用拡大につなげていきたい。
【高橋 正樹 議員】収益性にも目配りをした公共交通の整備を
安全で安心なまちづくりを進めるため、防犯対策用品の購入や設置費用の一部を補助してはどうか。
(回答)他市の事例などを情報収集しながら調査研究していく。
警察と連携して地域ごとに防犯訓練を行ってはどうか。
(回答)警察官を講師とした研修会を実施しており、実施地区の拡大を図るとともに、SNSの活用など、より効果的な研修方法を警察と協議していく。
(仮称)北くるりんの導入に向けて運行実験に取り組み、地域の実情を把握してはどうか。
(回答)地域や関係機関に意見を聞きながら、早期の運行実験開始を目指していく。
令和6年度のコミュニティサイクルの収支状況はどうか。また、今後どのようにサービスとしての魅力向上と収入増を図っていくのか。
(回答)6年度の維持管理費は約3530万円、収入は約1490万円であり、稼働率の向上や利用単価の上昇のため、台数やポート数のほか、観光者向けのサイクリングコースの設定なども検討していく。
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な推進に向けて、具体的にどのように取り組んでいるのか。
(回答)研究委嘱校では、探究学習や単元内自由進度学習に取り組んでおり、市内各校での特色ある実践につながっているが、さらなる支援や指導の充実に努めていく。
農業への理解が深まるように、市内の農業者や農業団体と連携し、小・中学生が長期間農業を体験できる仕組みを構築してはどうか。
(回答)農業への理解が深まることは次世代の担い手育成に向けて重要であるため、農業者や関係機関と連携して、農作業体験や農業を学ぶ機会の提供に努めていく。
コンテンツツーリズムを呼び込むため、作品に対して理解や関心の深い職員を担当部署に配置し、ファン目線の取り組みを展開してはどうか。
(回答)作品の注目状況を勘案しながら、職員の希望や全庁的な人事異動なども含めて検討していく。
ウォーカブルなまちづくりの今後の展開はどうか。
(回答)都市計画道路の整備が進むことで自動車交通の分散が図られるため、新たな民間投資や人の流れを呼び込み、エリア全体の価値を高めていく。
公金の資金運用戦略を見直し、収益性向上に向けた取り組みを行うべきではないか。
(回答)安全性や流動性を確保した預金での運用を行っているが、今後は他自治体の事例も参考に、預金以外の運用方法も検討していく。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-642-8404 ファクス番号:023-641-9160
giji@city.yamagata-yamagata.lg.jp